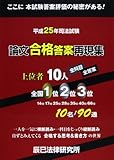1 司法試験お疲れ様でした!
受験生の皆さん,平成25年司法試験,本当にお疲れ様でした!手応えがなかった方が大半であるとは思いますが,まずは短答式の合格発表までゆっくり休んでくださいね。
司法試験後は様々な過ごし方がありますが,まずはとにかく遊んでください。自由に時間が使えることは,人生の中でそう多くはありません。一緒に勉強をしてきた仲間,これまで疎遠だった方々に会うなど,有効に時間を使うことをオススメします。
ちなみに,「司法試験後に勉強はした方がよいでしょうか?」という質問ですが,私は合格発表後でよいと思います。
2 平成25年司法試験公法系第1問は超良問
さて,試験のことは思い出したくもないという方もいらっしゃるかとは思いますが,気になってしまうのが人間の性。後進の受験生のためにも,平成25年司法試験の簡単な解説をしておきたいと思います。この解説は,あくまでも私個人の感想であり,当然のことながら司法試験委員の予定しているものとは異なります。しっかりとした解説は,出題の趣旨や採点実感等を踏まえてからとなりますので,その点はご了承ください。
(1) ウェブ上の解説など
現時点では,伊藤塾と辰已が速報を出していますね。
しかし,いずれも深い検討をしているとは思えず,表面的なものにとどまりますので,なんとも言えませんね。
充実した解説として,憲法ガールの著者のブログがありますので,そちらもあわせてご一読ください。
憲法ガールアンソロジーその1 「夢の続き ~平成25年新司法試験~」
※概ね同内容ですが,この記事とは以下の点がことなります。
・憲法ガールでは伝統的パブリックフォーラムに内包する危険とされているところ,この記事では集団暴徒化論として論じている点
・この記事ではルール理論を論じている点
・憲法ガールでは学生を大学の自治の主体として構成しているところ,この記事では大学の自治とは離れた通常の学問の自由の問題として扱っている点
・憲法ガールでは処分②について大学の裁量統制に流しているところ,この記事ではC教授の学問の自由を優先するとしている点
憲法ガール/法律文化社
![]()
¥2,520
Amazon.co.jp
(2) 再現答案
憲法の再現答案は,現時点では以下のものがアップされております。
・帆船ペスカトーラ(Pescatora)様
・平成25年司法試験、うけてきました様
(3) 総評
平成25年司法試験公法系第1問は,B県立大学の憲法ゼミの学生Aが「格差の是正」を訴えるデモ行進を企画したところ,第2回目までは許可されたものの,第3回目は不許可となってしまったことから,B県立大学で「格差問題と憲法」をテーマにした講演会の開催を計画するも,「政治的目的での使用」に該当するとして,教室使用申請を不許可とした,という事案でした(問題文はこちら)。
まず,形式面については,設問2の問い方が変更されました。すなわち,平成22年から平成24年までの設問2は「設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べなさい。」でしたが,平成25年からは「B県側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。」となりました。変更後の表記は,これまでの採点実感の記載を問題文に取り入れたものですから,実質的に回答内容を変更する必要があるわけではないでしょう。
次に,実質面についてですが,「表現活動と公の秩序」という超典型的な議論につき,ストレートに問う超良問であるといえそうです。これまでの(新)司法試験の中でも,特に実力の差がはっきりとでる最高峰のものといえそうです。具体的には,いわゆる予備校論証や予備校答案ばかり検討している方には厳しい問題であるのですが,しっかりと最高裁判例をあてはめまで読み込んでいる方にとっては,何を論じて欲しいかが明確な問題であったといえそうです。
問題意識としては,近年は反原発を含むデモ活動が活発であるところ,このような表現活動の規制につき,どのように「公の秩序」と調整するのかというところでしょうね。
3 3つの争点
本問では,大きく3つの点が争点となります。
第1は,【参考資料1】B県集団運動に関する条例(以下「条例①」という。)3条1項4号が,【参考資料2】B県住民投票に関する条例(以下「条例②」という。)14条1項2号,3号に掲げる行為をデモ行進にかかる申請の不許可事由としている点です。設問1の問題文には,「なお,道路交通法に関する問題並びにB県条例における条文の漠然性及び過度の広汎性の問題は論じなくてよい。」とのなお書があるところ,道路交通法に関する問題である法律と条例の関係(憲法94条),漠然不明確性ゆえに無効の法理,過度の広汎性ゆえに無効の法理は,問題にすべきではないことが明らかです。しかし,ここにいう「過度の広汎性ゆえに無効の法理」とは,いわゆる主張適格と結びついた文面審査の議論(広島市暴走族追放条例事件参照)であり,LRA審査(=必要性審査)を排除する趣旨ではないと読むべきでしょう。そうすると,表現の自由が重要な価値を有することを前提に,条例②14条1項2号「平穏な生活環境を害する行為」や同3号「商業活動に支障を来す行為」のような利益を不許可事由とすることの是非を端的に問うことは禁止されていないはずです。
第2は,B県公安委員会が,条例①に基づき,Aの第3回目のデモ行進に関する許可申請に対し不許可処分(以下「処分①」という。)をした点です。当該処分①は,Aの集団運動をする自由を侵害するものとして,憲法21条1項に反する,との主張があり得ます。
第3は,B県立大学が同大学教室使用規則に基づき,Aの「格差問題と憲法」をテーマにした講演会のための教室使用申請に対し不許可処分(以下「処分②」という。)をした点です。当該処分②は,Aの集会の自由及び学問の自由を侵害するものとして,憲法21条1項及び憲法23条に反する,との主張があり得ます。
なお,その他の問題点として,次のものが考えられますが,本問で論じる必要はないと思います。第1は,条例①が許可制を定めている点が事前抑制として憲法21条1項に反するとの主張ですが,新潟市公安条例事件(最大判昭29・11・24刑集8-11-1866)や東京都公安条例事件(最大判昭35・7・20刑集14-9-1243)【百選Ⅰ89】において合憲との結論は概ね一致しております。たしかに,双方とも,藤田八郎裁判官反対意見があるところですが,反対意見の主眼は,許可制そのものというより,許可要件が公安委員会の恣意的濫用を防止できるほど厳格でないことや,申請後に許可がないまま集団行動当日になってしまった場合の救済措置がない点を非難しています。また,LECの工藤北斗先生も指摘しているところですが,そもそもAは第1回目及び第2回目のデモ行進につき律儀に許可申請をしています。
したがって,無許可で集会をしたような新潟県公安条例事件とは異なり,Aには許可制そのものに対する不満があるとは思えません。第2は,
B県立大学教室使用規則が「政治的目的での利用は認めず,教育・研究目的での使用に限り,これを許可する」と定めている点が,学生の集会の自由を侵害するものとして憲法21条1項に反する,との主張もあり得ます。しかし,大学は政治的目的での活動をするような伝統的パブリックフォーラムではありませんね。また,
学生Aは憲法ゼミの一環として教室使用申請をしたにすぎず,「政治的目的」で本件集会を行いたいと主張したいようには思えません。このあたりの取捨選択は,「『憲法訴訟』感覚」(平成23年出題趣旨)が必要なところかもしれませんね。
4 争点①(条例①3条1項4号の合憲性)
(1) 被制約利益の特定
条例①3条1項4号が,条例②14条1項2号及び3号を不許可事由としていることから,B県公安委員会が「平穏な生活環境を害する行為」や「商業活動に支障を来す行為」に該当すると判断すると,屋外の公共の場所において集団運動をすることができません。したがって,条例①は,屋外の公共の場所において集団運動をする自由を制約しているといえます。
(2) 憲法上の保護の有無
東京都公安条例事件によると,集団運動の自由は,表現の自由として憲法21条1項により保障されます。厳密には,「その他一切の自由」に該当すると考えることになるでしょう。
東京都公安条例事件(最大判昭35・7・20刑集14-9-1243)【百選Ⅰ89】
「およそ集団行動は,学生,生徒等の遠足,修学旅行等および,冠婚葬祭等の行事をのぞいては,通常一般大衆に訴えんとする,政治,経済,労働,世界観等に関する何等かの思想,主張,感情等の表現を内包するものである。この点において集団行動には,表現の自由として憲法によつて保障さるべき要素が存在することはもちろんである。」
なお,動く集会として「集会の自由」で保障されると解する余地もありますね(宮沢俊義『憲法Ⅱ』〔新版〕378頁参照)。
(3) 規制態様
次に,規制態様を検討しましょう。
原告としては,内容着目規制であると主張したいところですが,条例①の適用対象は「屋外の公共の場所において集団による行進若しくは示威運動又は集会」であり,残念ながら,あらゆる表現行為が規制対象であると言わざるを得ません。活動家の鑑のような弁護士ならば,多くのデモ活動は反政府的言論をするものであるから,実質的には内容着目規制である,と主張するべきなのかもしれませんが,説得力を欠く印象があります。
また,「平穏な生活環境を害する行為」や「商業活動に支障を来す行為」という要件が漠然としており,恣意的濫用の危険性がある,と主張したいところですが,これは設問1では論じなくてよいとされている「条文の漠然性」の問題ですね。
(4) 違憲審査基準
そうすると,
原告は,内容中立規制のうち,時・場所・方法の規制に該当するとして,LRAの基準を主張するのが穏当ということになりましょうか。ただし,
私個人としては,表現の自由の内容中立規制であっても,B県公安委員会の恣意的な濫用を防止するべく,明白かつ現在の危険の法理を主張することもあり得るとは思います。実際に,新潟県公安条例事件においても,「これらの行動について公共の安全に対し明らかな差迫つた危険を及ぼすことが予見されるときは,これを許可せず又は禁止することができる旨の規定を設けることも,これをもつて直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限することにはならないと解すべきである。」として,明白かつ現在の危険の法理のように読める判示部分があります。
(5) 反論1-1:集団暴徒化論
これに対し,被告としては,いわゆる
集団暴徒化論を展開し,予防的な制約を認めるべきであるから,合理性の基準によるべきであるとの反論があり得ます。ここでは,東京都公安条例事件が参考になります。
東京都公安条例事件(最大判昭35・7・20刑集14-9-1243)【百選Ⅰ89】
「かような集団行動による思想等の表現は,単なる言論,出版等によるものとはことなつて,現在する多数人の集合体自体の力,つまり潜在する一種の物理的力によつて支持されていることを特徴とする。かような潜在的な力は,あるいは予定された計画に従い,あるいは突発的に内外からの刺激,せん動等によつてきわめて容易に動員され得る性質のものである。この場合に平穏静粛な集団であつても,時に昂奮,激昂の渦中に巻きこまれ,甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化し,勢いの赴くところ実力によつて法と秩序を蹂躙し,集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在すること,群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである。」
(6) 反論1-2:ルール理論
また,被告としては,いわゆる
ルール理論を展開し,県議会の立法裁量を強調することで,合理性の基準に持ち込むことも考えられます。ルール理論とは,戸別訪問事件(最判昭56・7・21刑集35-5-568)【百選Ⅱ173】伊藤正己裁判官補足意見を指します。
戸別訪問事件(最判昭56・7・21刑集35-5-568)【百選Ⅱ173】
伊藤正己裁判官補足意見
「選挙運動においては各候補者のもつ政治的意見が選挙人に対して自由に提示されなければならないのではあるが,それは,あらゆる言論が必要最少限度の制約のもとに自由に競い合う場ではなく,各候補者は選挙の公正を確保するために定められたルールに従つて運動するものと考えるべきである。法の定めたルールを各候補者が守ることによつて公正な選挙が行われるのであり,そこでは合理的なルールの設けられることが予定されている。このルールの内容をどのようなものとするかについては立法政策に委ねられている範囲が広く,それに対しては必要最少限度の制約のみが許容されるという合憲のための厳格な基準は適用されないと考える。」
本件において,条例①3条1項4号による制限は,条例②14条1項2号・3号を具体化したものであるところ,条例②は住民投票の際のルールを定めたものであることから,ルール理論の適用をすることができるとの反論は説得力があるように思います。
(7) 私の見解
もっとも,
集団暴徒化論については,批判が多いところです。また,
ルール理論についても,戸別訪問のように一律禁止により恣意的な運用はなされない場合と異なり,条例①及び②の要件は抽象的であり,
公安委員会が裁量を適切に行使できるか疑問が残るところです。法令審査の段階で十把一絡げに抽象的利益に基づく規制を認めることは,少数者の表現,特に反政府的な表現の自由が軽視される危険性が十分にありますから,個別的・具体的に当該集団運動が暴徒化するか否かについて,
客観的かつ慎重な判断を要求するべきでしょう。
表現の自由の重要性に照らすと,「交通事故」を制約理由とすることは格別,「騒音被害」や「売上げの減少」は,デモ行為に当然付随するものであることから,受忍限度にとどまるというべきでしょう。また,「交通事故」についても,集団運動がなくとも発生する可能性があるわけですから,今回の集団運動が原因となる事故が発生する等の事情がない段階では,抽象的な不安感にすぎません。そのため,このような抽象的な不安感で規制することは,生命・身体を保護するという目的との関係で,手段の実質的関連性を欠くといえるでしょう。
そこで,
条例②14条1項2号の「平穏な生活環境を害する行為」については
生命・身体・財産を害する限度,
同3号の「商業活動」については
積極的な営業妨害行為の限度で合憲である,というべきです。また,
条例①3条1項4号は,条例②14条1項2号及び3号に掲げる行為がなされることが「明らかであるとき」と規定しているところ,当該行為がなされる
明らかに差し迫った危険が客観的事実に照らして認められることをいう限度で合憲とするべきでしょう。
5 争点②(処分①の合憲性)
(1) 規制態様
処分①については,Aの集団運動をする自由が制約されていること,当該自由は表現の自由として憲法21条1項により保障されていることは,上記のとおりです。
処分①の最大の争点は,処分①が憲法上禁止されるべき言論弾圧か否かです。答案上では,内容着目規制か内容中立規制か否かという対立軸でもいいのかもしれません。
この点につき,原告であるAは,「デモ行進を不許可としたことは,県の重要な政策問題に関する意見の表明を封じ込めようとするものであり,憲法上問題がある」と発言していることから,処分①は言論弾圧であり憲法上禁止されるべきものであると主張するでしょう(少なくとも,内容着目規制であるから,その処分は極めて厳格な要件の下で許容される,と主張するべきです。)。
(2) 反論2:内容中立規制・間接的規制
これに対し,被告は,
言論弾圧ならば当初からデモ活動を許可しないであろうと考えられるところ,これまでAに対して2回のデモ行進を許可していたことから,禁止されるべき言論弾圧ではない,との反論が想定されます。また,第2回のデモ行進の際,実際に交通渋滞が発生したこと,市民や町内会から交通事故が起きることへの不安や騒音被害を訴える苦情や飲食店の売上げが減少したとの苦情がB県に寄せられたことから,処分①は,行動に伴う弊害を防止するための間接的制約である,との反論も想定されます。
意外と知られていないのですが,言論弾圧か否か,という点は,泉佐野市民会館事件(最判平7・3・7民集49-3-687)【百選Ⅰ88】で問題となりました。
泉佐野市民会館事件(最判平7・3・7民集49-3-687)【百選Ⅰ88】
「もとより,普通地方公共団体が公の施設の使用の許否を決するに当たり,集会の目的や集会を主催する団体の性格そのものを理由として,使用を許可せず,あるいは不当に差別的に取り扱うことは許されない。しかしながら,本件において被上告人が上告人らに本件会館の使用を許可しなかつたのが,上告人らの唱道する関西新空港建設反対という集会目的のためであると認める余地のないことは,前記一の4(一)(2)のとおり,被上告人が,過去に何度も,上告人国賀が運営委員である「泉佐野・新空港に反対する会」に対し,講演等のために本件会館小会議室を使用することを許可してきたことからも明らかである。また,本件集会が開かれることによって前示のような暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生ずる明らかな差し迫った危険が予見される以上,本件会館の管理責任を負う被上告人がそのような事態を回避し,防止するための措置を採ることはやむを得ないところであって,本件不許可処分が本件会館の利用について上告人らを不当に差別的に取り扱ったものであるということはできない。それは,上告人らの言論の内容や団体の性格そのものによる差別ではなく,本件集会の実質上の主催者と目される中核派が当時激しい実力行使を繰り返し,対立する他のグループと抗争していたことから,その山場であるとされる本件集会には右の危険が伴うと認められることによる必要かつ合理的な制限であるということができる。」
このように,泉佐野市民会館事件では,①泉佐野市は,原告らの団体に対し,過去に何度も市民会館を貸していたこと,②本件集会の開催により暴力の行使を伴う衝突が起こる等の事態が生ずる明らかな差し迫った危険が予見されることから,内容中立規制ではない,と判断されました。本件においても,①B県は過去に2回デモ行進を許可したことがあること,②少なくとも苦情が寄せられたことは認められます。
(3) 私の見解
もっとも,①の点については,泉佐野市民会館事件と異なり2回のみしか許可されていないこと,住民投票日が近づいてきて一層市民の関心が高まっているタイミングでの不許可処分であることから,内容中立規制であるとの論拠としては不足しているように思います。また,②の点についても,Aのデモは拡声器等を使用せず,ビラやゴミを配ることのない平和的なものであり,単なる苦情があったことをもってして,内容中立規制であるというのも厳しい感じがします。ただし,B県では「知事と県議会が激しく対立」していることから,公安委員会に特定の言論の弾圧をする動機があると認定することも困難であるように思います。これらを総合的の考えると,
少なくとも,禁止されるべき言論弾圧であるとはいえないという印象があります。
次に,処分①は,条例①及び②の要件に該当するかを論じる必要があります。上記の通り,
条例②14条1項2号の「平穏な生活環境を害する行為」については
生命・身体・財産を害する行為,
同3号の「商業活動」については
積極的な営業妨害行為,
条例①3条1項4号の「明らかであるとき」については,
明らかに差し迫った危険が客観的事実に照らして認められることをいうと解されます。
本件において,Aのデモ行進が不許可とされた主な理由は,①「交通事故が起きることへの不安」,②「騒音被害を訴える苦情」,③「飲食店の売上げが減少したという苦情」の3つですね。しかし,①については,交通事故は生命・身体の被害を伴うことから「平穏な生活環境を害する」といえそうですが,住宅街の道路を迂回路として使う車が増えただけで,実際に交通事故は発生していません。そのため,交通事故の発生を伴う行為が「明らかである」ということはできません。また,②については,Aらは拡声器等を使用していないことから,シュプレヒコールや参加者の行進する足音等が騒音とされているにすぎず,幹線道路の騒音に比して過大な騒音であるということもできません。そうすると,「平穏な生活環境を害する行為」ということはできません。さらに,③についても,売上げの減少は,幹線道路沿いという好立地であるならば,デモ行進に伴うものとして当然予想されるべきものであること,ビラやゴミをまき散らす等の積極的な営業妨害をしているわけではないことから。「商業活動を害する行為」とはいえません。
したがって,処分①は,条例①及び②の要件を満たさず,違憲・違法であるといえます。
6 争点③(処分②の合憲性)
(1) 被制約利益の特定
処分②により,学生Aは「格差問題と憲法」をテーマにした講演会(以下「本件講演会」という。)の開催をすることができないことから,Aが講演会を開催する自由が制約されているといえます。また,経済学部のゼミによる「グローバリゼーションと格差問題:経済学の観点から」をテーマとした講演会の教室使用願を許可したが,Aの申請を不許可としている点で,異別取扱いがあるといえます。
(2) 憲法上の保護
同自由は,Aが所属する憲法ゼミにおける学問研究の一環として本件講演会が開催されていることから,学問研究の自由として,憲法23条により保障されているといえます。また,異別取扱いをされない利益については,法の下の平等として,憲法14条1項により保護されているといえます。ただし,憲法14条1項の問題は,どちらかというとメインではないように思います。なぜなら,平等取扱いについては,表現の自由の内容着目規制の原則禁止として,憲法21条1項の中でも問題にすることができるためです。
(3) 教室使用規則の限定解釈
Aとしては,
教室使用規則にいう「政治的目的」とは,
カンパや投票を呼び掛けたり,一定の立場を支持したりする場合を指すところ,本件講演会は「格差問題と憲法」という憲法の研究活動であること,知事の施策方針に賛成する県議会議員と反対する県議会議員を講演者として招いていることから,「政治的目的」には該当しない,と主張するでしょう。
すなわち,大学の教室は,学生の自主的な研究活動を行うための施設であることから,原則として使用を許可すべきものであるところ,不許可処分が許容されるのは,学問の目的ではないことが明らかであるものに限定されるというべきです。本件において,Aは「格差の是正」を訴えるという特定の意見に基づくデモ行進を主催していましたが,本件講演会は「格差問題と憲法」という中立的なテーマであること,知事の施策方針に対し賛成・反対双方の立場の者を招いていること,権力の統制を目的とする憲法学は政府に対する批判を含む学問であることから,学問の目的でないことが明らかであるとはいえません。したがって,Aの教室使用申請は,「政治的目的」とはいえないことから,処分②は憲法23条に反する,との主張が可能ですね。
また,
仮に裁量統制審査であるとしても,判断の基礎となっている「Aらが中心となって行ったデモ行進が県条例に違反すること」は
事実誤認であり,「ニュースで流されたAの発言は県政批判に当たるものであること,また講演者が政治家であること」についても,憲法学の批判的性格であることや県政をよく知るものであることにつき
考慮不尽があると主張することも可能でしょう。
(4) 反論3-1:学問の自由の保護範囲外
これに対し,大学側から,
本件講演会は学問目的ではなく,政治的目的のものであるから,本件講演会をする自由は,学問の自由としては保障されず,集会の自由にすぎない,との反論が想定されます。集会の自由にすぎないとされると,大学は集会場所ではないことから,原告としては負け筋になるというわけです。
この点については,東大ポポロ事件(最大判昭38・5・22刑集17-4-370)【百選Ⅰ93】が参考になるでしょう。
東大ポポロ事件(最大判昭38・5・22刑集17-4-370)【百選Ⅰ93】
「学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく,実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には,大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しないといわなければならない。また,その集会が学生のみのものでなく,とくに一般の公衆の入場を許す場合には,むしろ公開の集会と見なされるべきであり,すくなくともこれに準じるものというべきである。
本件のA演劇発表会は,原審の認定するところによれば,いわゆる反植民地闘争デーの一環として行なわれ,演劇の内容もいわゆる松川事件に取材し,開演に先き立つて右事件の資金カンパが行なわれ,さらにいわゆる渋谷事件の報告もなされた。これらはすべて実社会の政治的社会的活動に当る行為にほかならないのであつて,本件集会はそれによつてもはや真に学問的な研究と発表のためのものでなくなるといわなければならない。また,ひとしく原審の認定するところによれば,右発表会の会場には,B大学の学生および教職員以外の外来者が入場券を買つて入場していたのであつて,本件警察官も入場券を買つて自由に入場したのである。これによつて見れば,一般の公衆が自由に入場券を買つて入場することを許されたものと判断されるのであつて,本件の集会は決して特定の学生のみの集会とはいえず,むしろ公開の集会と見なさるべきであり,すくなくともこれに準じるものというべきである。そうして見れば,本件集会は,真に学問的な研究と発表のためのものでなく,実社会の政治的社会的活動であり,かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて,大学の学問の自由と自治は,これを享有しないといわなければならない。したがつて,本件の集会に警察官が立ち入つたことは,大学の学問の自由と自治を犯すものではない。」
このように,東大ポポロ事件判決は,①反植民地闘争デーの一環として行われたこと,②松川事件(東北本線で起きた列車往来妨害事件に関する不当逮捕が問題となった事件)を題材にした演劇であること,③松川事件の資金カンパをしたこと,④渋谷事件の報告をしたことのすべてが実社会上の政治的社会的活動であると判断しています。本件においても,③カンパはしていないものの,①「格差の是正」を訴えるデモ行進がゼミの研究活動の一環であるシンポジウム「格差問題を考える」と連続性を有すること,②④第3回デモ行進の不許可処分を扱うことから,実社会の政治的社会的活動であるという反論は十分可能でしょう。
もっとも,
本件は,憲法ゼミの学生による講演会であること,担当であるC教授の承諾を得ていることから,大学公認の学内の劇団による演劇である東大ポポロ事件とは異なります。すなわち,演劇は公権力に対する批判を当然に含むものではありませんが,憲法学は国家権力を拘束する道具でもありますから,公権力に対する批判を当然に含みます。したがって,東大ポポロ事件のように,②松川事件や④渋谷事件を扱ったというだけで,政治的活動であるということは適切ではありません。また,①デモ行進では「格差の是正」という特定の立場を掲げているものの,本件講演会では「格差問題と憲法」という中立的な立場であり,双方の立場の県議会議員を招いていることから,本件講演会が「政治的活動」であるということは困難でしょう。
したがって,本件講演会を開催する自由は,学問の自由として保障されると解するべきでしょう。
(5) 反論3-2:大学の自治との調整
次に,大学側から,
裁判所が大学内部の処分につき積極的に判断をすることは,国家権力による大学の自治の侵害であるから,裁量統制審査に限定されるべきである,との反論が想定されます。
しかし,
大学の自治の趣旨は,国家機関による大学への介入を防止することで,個々の教授の研究の自由を保障する点にあると解されます。そのため,教室使用規則の該当性は,明らかに不合理でない限り,B県立大学ではなく,個々の教授の判断に委ねるべきです。実際に,B県立大学は,ゼミ活動目的での申請であり,かつ,当該ゼミの担当教授が承認していれば教室の使用を許可する,という運用を行ってきているのは,教授の学問の自由に対する配慮であるといえます。したがって,C教授の判断が明らかに不合理でない限り,教室使用申請を認めるべきである,ということができるでしょう。
(5) 反論3-3:「政治的目的」該当性
次に,大学側からは,
大学の自治を尊重するために,政治とは外見上も一定の距離を確保するべきであるから,教室使用規則にいう「政治的目的」とは,政治的活動のみならず,広く政治的活動との関連性が認められるものをいうと解するべきであり,C教授の判断は明らかに不合理である,との反論が想定されます。要するに,本件講演会が政治的社会的活動ではなく,学問の自由として保障されるとしても,教室使用規則による合理的な制限には服するという反論です。
この点については,寺西判事補事件(最大判平10・12・1民集52-9-1761)【百選Ⅱ196】が参考になります。
寺西判事補事件(最大判平10・12・1民集52-9-1761)【百選Ⅱ196】
「本件言動の裁判所法五二条一号該当性特定の法律を制定するか否かの判断は,国の唯一の立法機関である国会の専権に属するものであるところ,裁判官が,一国民として法律の制定に反対の意見を持ち,その意見を裁判官の独立及び中立・公正を疑わしめない場において表明することまでも禁止されるものではないが,前記事実関係によれば,本件集会は,単なる討論集会ではなく,初めから本件法案を悪法と決め付け,これを廃案に追い込むことを目的とするという党派的な運動の一環として開催されたものであるから,そのような場で集会の趣旨に賛同するような言動をすることは,国会に対し立法行為を断念するよう圧力を掛ける行為であって,単なる個人の意見の表明の域を超えることは明らかである。このように,本件言動は,本件法案を廃案に追い込むことを目的として共同して行動している諸団体の組織的,計画的,継続的な反対運動を拡大,発展させ,右目的を達成させることを積極的に支援しこれを推進するものであり,裁判官の職にある者として厳に避けなければならない行為というべきであって,裁判所法五二条一号が禁止している「積極的に政治運動をすること」に該当するものといわざるを得ない。」
寺西判事補事件判決は,パネリストとして出席しなくとも,①本件集会が本件法案を悪法と決めつけ,廃案に追い込むことを目的としていること,②少なくとも本件集会の趣旨に賛同する旨の発言をしたことから,「積極的に政治運動をすること」に該当するとしています。しかし,本件では,①講演会そのものは「格差の是正」を訴えるものではないこと,②Aが発言しているのはデモ行進の不許可についてであり,「格差の是正」については何らの主張をしていないことから,
本件講演会が「政治的目的」であるということは,やはり難しいでしょう。
したがって,C教授の判断が不合理であるとはいえず,処分②は違憲・違法であるといえそうです。
(6) 補論1:部分社会の法理
なお,大学側からの反論として,裁判所が教室使用申請処分という大学の内部行為につき判断をすることは部分社会の法理に反する,との反論を書くか悩んだ方もいらっしゃるかもしれません。しかし,富山大学専攻修了不認定事件(最判昭52・3・15民集31-2-280)によると,このような反論を認めることはできません。
なお,部分社会の法理を展開した富山大学単位不認定事件(最判昭52・3・15民集31-2-234)【百選Ⅱ201】と日付は同じですが,事件そのものは別物ですのでご注意ください。
富山大学専攻修了不認定事件(最判昭52・3・15民集31-2-280)
「国公立の大学は公の教育研究施設として一般市民の利用に供されたものであり,学生は一般市民としてかかる公の施設である国公立大学を利用する権利を有するから,学生に対して国公立大学の利用を拒否することは,学生が一般市民として有する右公の施設を利用する権利を侵害するものとして司法審査の対象になるものというべきである。」
7 補論2:国賠法上の違法性
国賠法上の違法性が,違憲性から直ちに認められるかは,違法・過失二元的判断と違法一元的判断との兼ね合いがあるところですね。いずれの立場に立つにせよ,処分①及び処分②の違法性については免責特権の問題となる国会による立法作用とは異なることから,本問の中心的な争点ではないでしょう。
8 まとめ
いかがでしょう。本問は,関連する判例法理を「はしご」することで解くことができるはずの問題であることが伝わりましたでしょうか。司法試験の憲法においては,短答式試験も含め,判例学習が超重要であることを実感していただければ幸いです。
このあたりは,法学セミナー701~702号の特集「司法試験採点実感にみる法律学修法」が非常に参考になります。憲法については,701号2頁以下「座談会 第1部「出題趣旨」「採点実感」を読む」(憲法は山本龍彦先生(慶應義塾大学准教授)が担当)や同号14頁以下の宍戸常寿先生の「憲法における事例問題の考え方/書き方」という記事です。
法学セミナー 2013年6月号: 司法試験採点実感にみる法律学修法 Part.1/日本評論社
![]()
¥1,400
Amazon.co.jp
また,法セミ701号123頁の「ブック・レビュー」では,私の師匠である小山剛先生が曽我部ほか『憲法論点教室』の書評を書かれております。基本書などについては,別に機会に紹介したいですね。
憲法論点教室/日本評論社
![]()
¥2,310
Amazon.co.jp
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()