君が代起立命令合憲判決が2つ立て続けに出ました。
1つは,最判平23・5・30(判決1),もう1つは,最判平23・6・6(判決2)です。
様々な意見や分析が飛び交っていますが、とりいそぎ私の見解を述べておこうと思います。
なお、新司法試験との関係では、この記事の3と4のみを読めば十分です。
1 事実の概要
判決1は,都立高等学校の教諭であったXが,卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱行為を命ずる旨の校長の職務命令に従わず,上記国歌斉唱の際に起立しなかったところ,その後,定年退職に先立ち申し込んだ非常勤の嘱託員及び常時勤務を要する職又は短時間勤務の職の採用選考において,都教委から,上記不起立行為が職務命令違反等に当たることを理由に不合格とされたため,上記職務命令は憲法19条に違反し,Xを不合格としたことは違法であるなどと主張して,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を求めている事案です。
なお,判決2も同様の事案です。
2 最高裁の判断(判決1)
(1) 保護範囲
Xの「卒業式における国歌斉唱の際の起立斉唱行為を拒否する理由について」の考え方は,「「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義等との関係で一定の役割を果たしたとする上告人自身の歴史観ないし世界観から生ずる社会生活上ないし教育上の信念等ということができる。」
(2) 制限
ア 職務命令の性質の点
①本件職務命令当時,公立高等学校における卒業式等の式典において,国旗としての「日の丸」の掲揚及び国歌としての「君が代」の斉唱が広く行われていたことは周知の事実である
②学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである
したがって,上記の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえない。
よって,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。
イ 外部からの認識という点
また,上記の起立斉唱行為は,その外部からの認識という点から見ても,特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,職務上の命令に従ってこのような行為が行われる場合には,上記のように評価することは一層困難であるといえるのであって,本件職務命令は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。そうすると,本件職務命令は,これらの観点において,個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。
ウ 行為の性質の点
もっとも,上記の起立斉唱行為は,教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。
そこで,このような間接的な制約について検討するに,個人の歴史観ないし世界観には多種多様なものがあり得るのであり,それが内心にとどまらず,それに由来する行動の実行又は拒否という外部的行動として現れ,当該外部的行動が社会一般の規範等と抵触する場面において制限を受けることがあるところ,その制限が必要かつ合理的なものである場合には,その制限を介して生ずる上記の間接的な制約も許容され得るものというべきである。
そして,職務命令においてある行為を求められることが,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり,その限りにおいて,当該職務命令が個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があると判断される場合にも,職務命令の目的及び内容には種々のものが想定され,また,上記の制限を介して生ずる制約の態様等も,職務命令の対象となる行為の内容及び性質並びにこれが個人の内心に及ぼす影響その他の諸事情に応じて様々であるといえる。したがって,このような間接的な制約が許容されるか否かは,職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。
(3) あてはめ
たしかに
本件職務命令に係る起立斉唱行為は,Xにとって,その歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為となるものである。
この点に照らすと,本件職務命令は,一般的,客観的な見地からは式典における慣例上の儀礼的な所作とされる行為を求めるものであり,それが結果として上記の要素との関係においてその歴史観ないし世界観に由来する行動との相違を生じさせることとなるという点で,その限りで上告人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があるものと
いうことができる。
しかし
①学校の卒業式や入学式等という教育上の特に重要な節目となる儀式的行事においては,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ることが必要である。
②住民全体の奉仕者として法令等及び上司の職務上の命令に従って職務を遂行すべきこととされる地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性(憲法15条2項,地方公務員法30条,32条)に鑑み,公立高等学校の教諭である上告人は,法令等及び職務上の命令に従わなければならない立場にある。
したがって,
本件職務命令は,公立高等学校の教諭である上告人に対して当該学校の卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とするものであって,高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い,かつ,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で,生徒等への配慮を含
め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るも
のであるということができる。
以上の諸事情を踏まえると,本件職務命令については,前記のように外部的行動の制限を介して上告人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面はあるものの,職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるものというべきである。
(4) 結論
以上の諸点に鑑みると,本件職務命令は,上告人の思想及び良心の自由を
侵すものとして憲法19条に違反するとはいえないと解するのが相当である。
3 ピアノ判決との違い
朝日新聞には、ピアノ判決が思想良心の自由を制限しないとしていたのに対し、起立命令判決は間接的規制を認めた点で進歩した、という教育法学者の意見が掲載されていました。
しかし、残念ながらこの分析は甘いと言わざるを得ません。
そもそも,本判決は、ピアノ判決を引用していません。
また、伴奏行為は、君が代斉唱にほぼ必然的に付属する行為であること、歌詞を伴わない機械的行為であることから、思想良心の表明であるということは困難です。
これに対し、起立斉唱は、一般的客観的に、少なくとも敬意を表す行為といえます。
そうすると、制約か否かについて、ピアノ判決から進歩したのではなく、単なる事案の違いにすぎません。
4 違憲審査の手法
さて、本判決の分析の目玉となるであろう、違憲審査の手法について分析きましょう。
まず、本件は直接的には「職務命令」の合憲性が問題とされています。
職務命令は、要件効果の定まらない行政処分であるため、行政裁量が働く領域です。
そうすると、違憲審査の観点は、裁量型にシフトしてしまうとも思えます。
下級審には、判断過程審査を採用したものがあるのも、そのあらわれです。
しかし、本判決は裁量型ではありません。
なぜなら、本件職務命令の問題点は、裁量の行使ではなく、それが寄って立つ通達そのものにあるからです。
そこで、本判決を注意深く読むと、単なる職務命令ではなく、「通達を踏まえた職務命令」について合憲性を審査しています。
このように、違憲判断の対象と違憲の問題点との間には、ズレがあるのです。
それゆえ、処分違憲には目的手段審査は使えない、という定式化は危険です。
違憲審査の手法は、違憲の問題点がどこか、という観点から決まるべきものです。
次に,本判決は,いわゆる「間接的規制」であるというロジックから,審査密度を総合衡量まで低下させています。
本判決の引用している判決は,謝罪広告事件,猿払事件,個別訪問事件2つです。
これらのうち,猿払事件と個別訪問事件は,ともに間接的規制であることを理由に,いわゆる猿払基準を立てていました。
君が代ピアノ判決も,本判決と同じ4つの判例を引用しています。しかし,ピアノ判決は「不合理ではない」という審査をしている点で,猿払基準ではありません。
また,本判決は総合衡量であり,ピアノ判決基準でも猿払基準でもありません。
そうすると,これらの判決は,「間接的規制の場合は,とりあえず審査密度は下がります」という点でのみ,共通するものであるといえます。
その上で,猿払基準→本判決→ピアノ判決の順に,審査密度は低くなる考えることもできるでしょう。
5 本判決の問題点
では、本判決は何ら問題がないのでしょうか。
憲法学の立場からすれば、結論が不当であるとして様々な非難がなされるかもしれません。
しかし、私は、「思想良心の自由との関係では」、結論は不当ではないと考えています。
教師の個人的感情の類を思想良心の自由として保護し、職務命令に従わないことを正当化することは、教育制度の崩壊を招くでしょう。
仮に、君が代斉唱拒否を認めるとすれば、他の信条に基づく行為をどこまで思想良心の自由として保護すべきかという問題が生じかねません。
思想良心の自由との関係で非難すべきは、その判断枠組みです。
すなわち、本判決は、違憲審査基準を定立せず、間接的規制ゆえ総合衡量という一般論を展開しています。
その上で、本来は審査密度を下げるための理由とすべき、全体の奉仕者論をあてはめレベルで使っています。
これでは、一般人に対する起立命令も、同様の総合衡量でなされてしまうおそれが-理論的にはーあります。
やはり、全体の奉仕者論は、審査密度決定の前で論じるべきであり、一般論の不当な拡大を防止するべきであったといえます。
結論に関しては,様々な議論がなされていますので,司法試験との関係で注目すべき話題ですね。
iPhoneからの投稿
君が代起立斉唱命令合憲判決について その1
新司法試験短答式の勉強法
0 はじめに
短答式の成績通知がありました。
これを受けて,ウェブ上では様々な勉強方法の公開,教示がなされています。
そこで,私も便乗して,短答式の勉強方法についてご紹介したいと思います。
なお,私の短答式の点数は,292点/350点,48位/8721人中でした。
内訳は,公法系83点/100点,民事系131点/150点,刑事系78点/100点です。
1 開始時期(試験前年の9月~)
まず,開始時期ですが,ロー3年生の夏休み後半からでした。
この時期は,辰巳の科目別体系別過去問集を2周しました。
2周目は,間違ったところだけしかしませんでした。
なお,「間違った」とは,単に正解を間違えたものの他,わからない肢があった場合,悩んで答えを出した場合,理由がわからなかった場合を含みます。
私は,次のように記号を使い分けて,メリハリをつけていました。
◎ すべての肢について正確に理解した上で正解を導けた。
○ わからない肢があったが正解を導けた。
△ 正解を導けたが,理由づけが異なった,あるいは,勘で正解した。
× 間違えた。
C 間違えたが,問題の読み違いやケアレスミスに起因した。
これらの認定は,厳格に行いましょう。
自分に甘くすると,後々できなくて後悔しますから。
2回目以降は,○,△,×,Cをやります。
まずは,法律の全体像と問われる知識の位置づけを確認することが肝要です。
この時期は,これ以上のことをする必要はないと思います。
2 肢別
10月頃になると,新年度版の肢別本が発売されます。
そこで,これを即座に買って,とりあえず1周します。
チェック欄は,上記の△,×,Cのみです。
なんとなく正解したもの,自信がなかったものは,すべて△です。
必ず自分に厳しくしましょう。
この時期は,とりあえず回すだけでよいと思います。
1周目では,壊滅的にできない分野が明らかになります。
△,×がページを埋め尽くすことはザラです。
そんなことにめげても仕方ありません。
2周目以降は,正解した場合,△,×,Cの上に○をします。
間違えた場合は,横に△,×,Cを書きます。
そして,△,×,Cがなくなるまで回します。
3 基本書チェック
この場合,当該分野の基本書をざっと読みましょう。
択一用基本書は,薄く,定評あるものにしましょう。
一例として,私が使用した択一用基本書を科目別に掲載します。
憲法
芦部憲法
憲法 第五版/芦部 信喜
¥3,255
Amazon.co.jp
憲法判例(反対意見,補足意見,意見のチェック)
憲法判例 第6版/戸松 秀典
¥3,045
Amazon.co.jp
行政法
サクハシ行政法
行政法/櫻井 敬子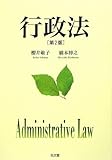
¥3,465
Amazon.co.jp
行政法判例ノート
行政判例ノート/橋本 博之
¥2,940
Amazon.co.jp
民法
入門民法(全)/潮見佳男
¥3,990
Amazon.co.jp
会社法
会社法 第2版 (LEGAL QUEST)/伊藤 靖史
¥2,940
Amazon.co.jp
商法
商法総則・商行為法 (有斐閣法律学叢書)/近藤 光男
¥2,940
Amazon.co.jp
手形小切手法(最初のまとめ部分のみ)
商法 [総則・商行為]・手形法小切手法 (伊藤真試験対策講座 8)/伊藤 真
¥3,990
Amazon.co.jp
民事訴訟法
民事訴訟法講義案(再訂補訂版)司法協会
刑法
刑法/山口 厚
¥3,360
Amazon.co.jp
刑事訴訟法
入門刑事手続法 第5版/三井 誠
¥3,045
Amazon.co.jp
4 判例六法発売
11月になると,判例六法が発売されます。
それに合わせて,間違えたところだけ肢別本の2周目をします。
その際,また間違えたところを判例六法にマーキングします。
3周目にも間違えたところは,赤ペンでサイドラインを引きます。
なお,判例百選は,時間との関係もありますので,次の科目は判例六法の抜粋部分で済ませます。
商法,手形小切手法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法。
ただし,なんだこれは?という判決があったら,時の判例の解説を読むべきでしょう。
今でも忘れないのは,弁護人の選任の効力の終期に関する,最決平4・12・14です。
なぜその結論になるのか,どういった経緯で論点となったのかを調べることで,確かな知識を身に着けることができます。
最新の「時の判例Ⅵ」のみならず,Ⅰ~Ⅴもそろえておくと論文対策に有用です。
私は,Ⅵを重判の代わりに使っていました。
最高裁 時の判例(平成18年~平成20年)6 (ジュリスト増刊)/著者不明
¥3,600
Amazon.co.jp
5 試験直前期(5月以降)
5月は,本試験過去問の科目別を1日1冊終わらせます。
この時点で△と×ところには付箋を貼っておきましょう。
これで最終チェック用の準備は終了です。
6 中日
司法試験は5日間あり,そのうち3日目は休みです。
この日は,午前から夕方までは短答式対策,夜は刑事系の論証チェックをしました。
また,
4日目の刑事系は早く終わるので,帰宅後に短答式対策が可能です。
ここでは,先ほど用意した,付箋でいっぱいの科目別過去問集を解き,条文を判例六法を読みます。
これだけでかなり違うと思います。
7 予備校教材について
私は,予備校の出版している択一六法,情報シートの類は,ほとんど使いませんでした。
使ったといえば,商法と民法ですが,最終的には開きませんでした。
なぜなら,あんなに分厚いものを7冊も読める自信がなかったからです。
はっきり言って情報過多ですし,基本的な知識を身に着けているならば,その部分は不要です。
よくまとまっているとは思いますが,掘り下げるには浅すぎ,対策としては広すぎる感覚があります。
とりあえず,過去問,百選,条文以外の知識は横においておくのが賢明です。
また,予備校の模試の復習もしませんでした。
予備校問題は,バイトが制作しているものであり,また,制作上の制限があるため,本試験のレベルとは明らかに離れています。
重箱の隅をつつくか,下品なひっかけ問題が多いような気がします。
時間があればよいのですが,あいにく彼らに付き合っている暇はありません。
さらに,タクティクスのような本試験形式とタイプは,間違えた知識のチェックが難しいように思います。
上記の△と○と◎を区別することができれば問題ないのでしょうが,人間そうはいきません。
本試験形式のタイプは,知識の穴ができてしまうように感じるため,お勧めできません。
このように,予備校関連教材は,あまり期待しない方がよいと思います。
以上です。
短答式の結果には運の要素もあります。
足切りを回避するためなら,ここまでする必要はありません。
大切なのは,自分が間違えているところを把握し,繰り返すことで知識を確実にすることです。
平成23年司法試験予備試験 その1 憲法
0 近況報告
真夏日のような暑さが続き,夏の到来を感じさせます。
昨年の夏休み,水着で学校へ行き,誰もいない自習室で机や椅子でバリケードを作りながら水鉄砲を撃ちあっていたのが懐かしいです。
新司法試験受験生の企業法務志望の方は,就職活動が大詰めの頃と思います。
私も,いくつかの説明会,個別訪問に参加しましたが,実務家の方は魅力的な方が多いです。
さて,本日は,久しぶりに記事を書こうと思います。
題材は,昨日実施された司法試験予備試験の憲法の問題です。
1 概要
本問は,国立法科大学院が,入学定員の1割について女性の受験生を優遇する入学者選抜制度の是非を問うものです。具体的には,国立A法科大学院が,入学定員200名のうち180名に関しては性別にかかわらず成績順に合格者を決定し,残りの20名に関しては成績順位181位以下の女性受験生のみを成績順位合格させるという制度を創設したところ,男性であるBは,成績順位181位で不合格となった,という事案でした。
主要な論点は,積極的差別是正(アファーマティブ・アクション)に関する憲法14条1項の審査基準です。その他,当該制度を無効とすることでBは入学できるか,入学者選抜の制度構築は大学の自治であるとして司法権の介入をどの程度認めるべきかも問題となり得ます。
類似の事件としては,入学者選抜における人種的少数者に対する優遇制度が問題となったGrutter v. Bollinger, 539 U.S. 306やGratz v. Bollinger, 539 U.S. 244というアメリカ合衆国の事件が挙げられます。
2 形式面
設問1は,Bの弁護士の立場から,訴訟選択,憲法上の主張を,設問では,原告側の憲法上の主張とA法科大学院側の憲法上の主張との対立軸を明確にした上で,あなた自身の見解を述べなさい,というものでした。旧司法試験のように「憲法上の問題点について論ぜよ」として,特定の立場のみを問うものではなく,新司法試験のように,複眼的思考が求められています。ただし,新司法試験が「あなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べなさい」と問うていることと比較すると,「対立軸を明確にした上で」としていることから,何が争点となるかを端的に指摘すればよく,深い反論までは求められていないでしょう。
3 内容面
(1) 設問1
Bとしては,A法科大学院で勉強をしたいと考えているため,A法科大学院に対して,①2008年度入学試験不合格処分の取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)及び同試験合格処分の義務付け訴訟(同法3条6項2号)を併合提起すること,②同取消訴訟及び合格者という公法上の地位の確認訴訟(同法4条後段)を併合提起すること,③不合格処分が無効であることを前提に,同地位確認訴訟を提起することが考えられます。③は不合格処分が無効であるとの主張は現実的ではないこと,②は合格者たる地位は合格処分がなければ得られないことから,①が妥当でしょう。
※ 補足(2011年7月20日追加)
訴訟選択は議論があるところです。
群馬大学医学部を受験した主婦が,合格点に達していたにもかかわらず,面接試験で落とされたとして,年齢による差別だと主張して,入学許可を求めた事件(群馬大事件)では,民事上の請求として扱われています(東京高判平19・3・29)。
具体的には,出願は,懸賞広告契約類似の無名契約であると構成しています。
その上で,入学許可は試験合格のみならず各種費用の納付が必要であることを指摘して,請求を退けようとしています。
他方,合格の意思表示を求める請求と構成できるとして,民事上の請求として実体判断をしています。
本件も同様に扱うことができるのではないかと思います。
そうすると,不合格処分の公定力はなくなるため,合格の意思表示を求める請求,地位確認請求も可能になります。
ただし,この場合,出願が契約の申込みである以上,本件制度は契約内容にすぎません。百里基地訴訟を参考にすると,この場合は私人間効力の問題となるでしょう。民事請求であるが憲法は適用される,という論理は少し落ち着きが悪いように思います。
そうすると,日産自動車事件を参考に,平等違反の議論を組み立てることになるでしょう。
憲法上の主張としては,まず,当該入学者選抜制度は,性別を基礎とした合理的理由のない差別であり,憲法14条1項に反し違憲・無効であることを主張することが考えられます。具体的には,差別が憲法14条1項後段列挙事由の「性別」に基づく「疑わしい区別」であるから「厳格な合理性の基準」を適用するべきであると主張することが考えられます(性別は人種と異なり,肉体的・条件的差異があるため「厳格審査基準」は妥当しないというのが,学説の趨勢です。)。その上で,「法曹界における女性の増加」は正当な目的ではあるが,①【参考資料】によると昭和60年から法曹人口に占める女性の割合は増加していること,②女性の割合が低いのは差別があるためではなく,女性が男性よりも法曹を志望しない点に起因することから,当該目的を促進するべき立法事実は存在せず,重要な目的とはいえないと主張することになるでしょう。
次いで,当該制度が違憲無効であるならば,成績順位181位以下200位以上が合格であるから,Bは合格していることを主張することが考えられます。
(2) 設問2
第1の対立軸は,当該入学者選抜制度がアファーマティブ・アクションとして「合理性の基準」が適用されるか,という点でしょう。
アファーマティブ・アクションとは,差別が長年にわたって行われていたことを是正するものであるところ,法曹界ではそのような差別があったという事実はありません。また,アファーマティブ・アクションについて緩やかな審査基準を適用するべきであるとの主張の理由は,逆差別については多数派が民主制の過程で是正することができる点にあります。法曹を目指す男性が民主制の過程に訴えることは困難ではないため,原則どおり「厳格な合理性の基準」が適用されると考えるべきでしょう。
第2の対立軸は,入学者選抜の制度構築は大学の自治に属するものであるから,司法権の介入をどの程度認めるべきか,という点でしょう。
前提として,入学試験は部分社会に入るか否かを決めるものですから,内部処分と異なり,部分社会の法理は妥当しません。大学が国民の学習権を実現するものであることに照らすと,国立大学がどのような生徒を採用するかは,まったくの自由裁量ではなく,大学の設置目的に沿った形でなければなりません。また,学問に関する専門技術的裁量を尊重する理由もありません。それゆえ,大学内の内部人事,施設管理,学生管理等と異なり,大学の自治を尊重するよりも,司法審査の介入を通常通り認めることが,裁判を受ける権利の観点からも妥当です。
第3の対立軸は,多様性を考慮することが重要な目的といえるか,という点でしょう。
法科大学院は新司法試験の受験資格を付与するものであること,研究機関であることから,学力による選抜が原則となります。しかし,法曹が多様な人々とかかわる職業であることに照らすと,多様性の確保は重要な要素です。また,法曹界で女性が歴史的に差別されていないとしても,日本の人口比率に比べて女性の志望者が少ないことから,「法曹界における女性の増加」は,重要な目的であるといえます。さらに,受験生の男女比が2対1であることを考えると,成績順位が181位以下の者について入学定員の1割のみを優先枠とすることは,相当性を有するといえます。
なお,「本来合格水準に到達しない女子学生を合格させてしまうことになる。そのような者が新司法試験に合格する可能性は低いのであるから,実効的な手段といえず,目的と手段との実質的関連性は存しない。」とのあてはめがあり得ますが,目的は「法曹界における女性の増加」であるため,手段との関連性のうち,因果関係としての適合性は概ね問題ありません。
問題の核心は,①女性を理由に優遇することの是非,②優遇の程度の是非です。
以上より,合憲との結論を導くことができます。
4 総評
本問は,近年の事例を題材にして,訴訟選択,救済方法,対立軸を考えた上で,基本的知識の深い理解を問う良問であったといえます。
君が代起立斉唱命令合憲判決について その2
直接的制約と間接的制約に関する覚書
一連の君が代起立斉唱判決の分析
1 はじめに
平成15年10月23日,東京都教育委員会(都教委)の教育長から,「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」(本件通達)が発せられた。この通達に基づき起立斉唱行為を命ずる旨の職務命令がなされ,これに違反した都立高校教員に対する再雇用拒否(最判平23・5・30(判決①),最判平23・6・6(判決②)),市立中学校教員に対する戒告処分とその審査請求棄却採決(最判平23・6・14(判決③)が,憲法19条に違反するか争われたが,上記判決はすべて合憲であると判断した。
また,立て続けに類似の事件に関する判決が下された。1つは,平成12年12月26日,広島県教育部長が発した同旨の通達に基づき同旨の職務命令がなされ,これに違反した広島県立学校の教職員に対してなされた戒告処分の憲法19条適合性が争われた(最判平23・6・21(判決④))。もう1つは,平成16年3月11日に行われた都立高校の卒業式当日にビラを配布し,校長らに退場を要求されたにもかかわらず怒鳴り声を上げてこれに抵抗した被告人を威力業務妨害罪で処罰することの憲法19条適合性が争われた(最判平23・7・7(判決⑤))。これらの判決も合憲であると判断した[1]。
判決①~⑤に先立つ君が代をめぐる判決としては,最判平19・2・27(ピアノ判決)がある。ピアノ判決は,憲法19条の権利侵害を認定しなかった。
「本件入学式の国歌斉唱の際のピアノ伴奏を拒否することは,上告人にとっては,上記の歴史観ないし世界観に基づく一つの選択ではあろうが,一般的には,これと不可分に結び付くものということはできず,上告人に対して本件入学式の国歌斉唱の際にピアノ伴奏を求めることを内容とする本件職務命令が,直ちに上告人の有する上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと認めることはできない」。
これに対し,判決①~④は,間接的な制約を認定した。
判決①は次のように説示した。「上記の起立斉唱行為は,教員が日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体には含まれないものであって,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる「日の丸」や「君が代」に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」判決②~④も同様に論じ,判決①を引用している。
しかし,判決②の裁判官宮川光治の反対意見は,間接的な制約との言葉を使わず,また,猿払基準を使わずに厳格審査基準を適用せよと論ずる。
本件通達の「意図するところは,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き,その歴史観等に対する否定的評価を背景に,不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制しようとすることにあるとみることができる。本件各職務命令はこうした本件通達に基づいている。」「上告人らの不起立不斉唱という外部的行動は上告人らの思想及び良心の核心の表出であるか,少なくともこれと密接に関連している可能性があるので,これを許容せず上告人らに起立斉唱行為を命ずる本件各職務命令は憲法審査の対象となる。そして,上告人らの行動が式典において前記歴史観等を積極的に表明する意図を持ってなされたものでない限りは,その審査はいわゆる厳格な基準によって本件事案の内容に即して具体的になされるべきであると思われる。本件は,原判決を破棄し差し戻すことを相当とする。」
本稿では,これらの判決の制限態様に関する議論を整理したい。
2 多数意見のロジック
判決①の多数意見の骨子は,次のとおりである。
「このような間接的な制約について検討するに,個人の歴史観ないし世界観には多種多様なものがあり得るのであり,それが内心にとどまらず,それに由来する行動の実行又は拒否という外部的行動として現れ,当該外部的行動が社会一般の規範等と抵触する場面において制限を受けることがあるところ,その制限が必要かつ合理的なものである場合には,その制限を介して生ずる上記の間接的な制約も許容され得るものというべきである。そして,職務命令においてある行為を求められることが,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求められることとなり,その限りにおいて,当該職務命令が個人の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があると判断される場合にも,職務命令の目的及び内容には種々のものが想定され,また,上記の制限を介して生ずる制約の態様等も,職務命令の対象となる行為の内容及び性質並びにこれが個人の内心に及ぼす影響その他の諸事情に応じて様々であるといえる。したがって,このような間接的な制約が許容されるか否かは,職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」
その上で,判例①は,憲法19条に違反しないとの結論は,謝罪広告事件,猿払事件,2つの個別訪問事件の趣旨に徴して明らかであるとする。謝罪広告事件は,憲法19条に関連するものとして挙げられていると考えられる。他方で,猿払事件,2つの個別訪問事件は,間接的規制のものとして挙げられていると考えられる。
猿払事件判決は,何の理由もなく,「禁止の目的,この目的と禁止される政治的行為との関連性,政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが必要である」として,合理性の基準を採用した。これに対し,多数意見は「間接的な制約」に「総合較量」という基準なきアドホックバランシングを採用する理由を,職務命令の内容,目的,制限の態様,対象行為の内容,性質,影響には種々様々なものがあることに求めた。
しかし,これらは立法裁量論に流れる理由としては納得しうるが,総合較量に逃げ込む理由としては不十分である。
3 裁判官宮川光治の反対意見(判決②)
(1) 骨子
判例②の宮川反対意見の骨子は,次の通りである。
本件通達の「意図するところは,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き,その歴史観等に対する否定的評価を背景に,不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制しようとすることにあるとみることができる。本件各職務命令はこうした本件通達に基づいている。」
「上告人らの不起立不斉唱という外部的行動は上告人らの思想及び良心の核心の表出であるか,少なくともこれと密接に関連している可能性があるので,これを許容せず上告人らに起立斉唱行為を命ずる本件各職務命令は憲法審査の対象となる。そして,上告人らの行動が式典において前記歴史観等を積極的に表明する意図を持ってなされたものでない限りは,その審査はいわゆる厳格な基準によって本件事案の内容に即して具体的になされるべきであると思われる。」
以下,詳細を抜粋する。
(2) 憲法19条の権利侵害認定は主観的に行われるべきである
「多数意見は,式典において国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観それ自体を否定するものではないとしている。多数意見は,式典における起立斉唱行為を,一般的,客観的な視点で,いわば多数者の視点でそのようなものであると評価しているとみることができる。およそ精神的自由権に関する問題を,一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当でないと思われる。」「思想及び良心として深く根付き,人格的アイデンティティそのものとなっており,深刻に悩んだ結果として,あるいは信念として,そのように行動することを潔しとしなかった場合,そういった人達の心情や行動を一般的ではないからとして,過小評価することは相当でないと思われる。」
(3) 不起立行為が憲法19条として保護される条件としての「真摯性」
「本件では,上告人らが抱いている歴史観ないし世界観及び教育上の信念が真摯なものであり,思想及び良心として昇華していると評価し得るものであるかについて,また,上告人らの不起立不斉唱行為が上告人らの思想及び良心の核心と少なくとも密接に関連する真摯なものであるかについて(不利益処分を受容する覚悟での行動であることを考えるとおおむね疑問はないと思われるが),本件各職務命令によって上告人らの内面において現実に生じた矛盾,葛藤,精神的苦痛等を踏まえ,まず,審査が行われる必要がある。こうした真摯性に関する審査が肯定されれば,これを制約する本件各職務命令について,後述のとおりいわゆる厳格な基準によって本件事案の内容に即して具体的に合憲性審査を行うこととなる。」
(4) 侵害態様の直接性,目的志向性?
「国旗及び国歌に関する法律施行後,東京都立高等学校において,少なからぬ学校の校長は内心の自由告知(内心の自由を保障し,起立斉唱するかしないかは各教職員の判断に委ねられる旨の告知)を行い,式典は一部の教職員に不起立不斉唱行為があったとしても支障なく進行していた。」
「都教委は教職員に起立斉唱させるために職務命令についてその出し方を含め細かな指示をしていること,内心の自由を説明しないことを求めていること,形から入り形に心を入れればよい,形式的であっても立てば一歩前進だなどと説明していること,不起立行為を把握するための方法等について入念な指導をしていること,不起立行為等があった場合,速やかに東京都人事部に電話で連絡するとともに事故報告書を提出することを求めていること等の事実が認められるのであり,卒業式等にはそれぞれ職員を派遣し式の状況を監視していることや,その後の戒告処分の状況をみると,本件通達は,式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き,その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に,不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができると思われる。」
なお,この部分は,本件職務命令に対する目的志向性の評価により,判断が分かれる。判例①の裁判官竹内行夫の補足意見は,「表見的には外部的行動に対する制限であるが,実はその趣旨,目的が,個人に対して特定の歴史観等を強制したり,あるいは,歴史観等の告白を強制したりするものであると解される場合には,直ちに,思想及び良心の自由についての制約の問題が生ずることになるが,本件職務命令がそのようなものであるとは考えられない」として,目的志向性がないと判断している。
(5) 厳格審査における考慮事項
「本件各職務命令の合憲性の判断に関しては,いわゆる厳格な基準により,本件事案の内容に即して,具体的に,目的・手段・目的と手段との関係をそれぞれ審査することとなる。目的は真にやむを得ない利益であるか,手段は必要最小限度の制限であるか,関係は必要不可欠であるかということをみていくこととなる。結局,具体的目的である「教育上の特に重要な節目となる儀式的行事」における「生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ること」が真にやむを得ない利益といい得るか,不起立不斉唱行為がその目的にとって実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白で,害悪が極めて重大であるか(式典が妨害され,運営上重大な支障をもたらすか)を検討することになる。その上で,本件各職務命令がそれを避けるために必要不可欠であるか,より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等,会場の外における役割を与え,不起立不斉唱行為を回避させることができないか)を検討することとなろう。」
(6) 小括
宮川反対意見は,真摯な不起立行為が憲法19条により保護されること((3)参照)を前提に,①権利侵害の主観性((2)参照),②侵害の目的志向性((4)参照)を根拠として,厳格な審査を要求しているといえる。
なお,「上告人らの行動が式典において前記歴史観等を積極的に表明する意図を持ってなされたものでない限りは」という留保を付して,「その審査はいわゆる厳格な基準によって本件事案の内容に即して具体的になされるべきである」と説示した理由は,「積極的に表明する意図をもってなされた」場合,「国家による作為の強制」ではなく,「国家による不作為の要請」となる点にあると考えられる。
とりあえず以上です。
次回は,裁判官田原睦夫の反対意見を分析します。
[1] 判決⑤は,判決①~④と異なり刑事事件である。それゆえ,ピアノ判決,判決①~④を引用せず,鉄道駅校内におけるビラ配布につき鉄道営業法や不退去罪で処罰することの合憲性が問題となった吉祥寺事件(最判昭59・12・18刑集38-12-3026)が参照されている。合憲性の検討アプローチが異なるため,本稿では検討対象から外す。
憲法と哲学 その1
今日は,法学徒にはあまりなじみのない「哲学」について書きたいと思います。
昨年,ハーバード大学教授のマイケル・サンデルの「Justice」(邦題「これからの「正義」の話をしよう」)が流行しましたね。
もちろん,私も流行りにのって読みましたが,学部時代から政治哲学を学んでいました。
プラトン,アリストテレス,ルネ・デカルト,マックス・ヴェーバー,カール・ポパー,ハンナ・アーレント,アンソニー・ギデンズ,ヘーゲル等についての概論は知っているつもりです。
実は,私が憲法にシンパシーを感じたのは,哲学的側面にあります。
我が国の哲学者,竹田青嗣によれば,「哲学」とは,「普遍的な考え方の原理を探す言語ゲーム」です。
哲学が生まれたのは,諸文化の交易の中心地,小アジアのイオニア地方であるとされます。
各文化は,異なった宗教,物語,神話を持っているために,共通認識を生むことが難しかったのです。
そこで,このような「物語性」に依拠しない,抽象概念を使った世界説明,原理の探求をすることで,共通認識を生もうとしたわけです。
翻って,国家には,様々な人がいます。
国家を創造するために,「あなたを認めるから,私を認めてほしい」という「相互承認」が不可欠です。
各人が好き勝手すれば,他の人が迷惑を被るおそれがあります。
人は,「平均的な人」から,何らかの意味必ずズレています。
特に,多民族国家であるアメリカ合衆国では,そのズレの幅は大きかったに違いありません。
我が国のように「ほぼ」単一民族国家である場合,そのズレは異民族国家よりは少ないでしょう。
しかし,実際には,在日朝鮮人,アイヌ民族,沖縄民族等の多民族は存在しますし,日本人にもさまざまな考え方を有する人がいます。
それゆえ,我が国においても「相互承認」は必要となるのです。
では,そのズレがあった場合,どうすればよいのでしょうか?
この場合,我慢して「平均的な人」に合わせろという選択肢と,一定の限度でズレを認めるから他人のズレを認めなさいという選択肢があります。
憲法13条前段が「個性の尊重」を定めていますので,我が国の憲法が後者(ズレを認める)であることは容易に想像がつきます。
そうすると,憲法というのは,「相互承認」の結果生まれたと考えられるわけです。
「相互承認」を「社会契約」の具体的な内容と理解することも可能でしょう。
なお,このあたりは,竹田青嗣「人間の未来―ヘーゲル哲学と現代資本主義」(ちくま新書・2009年)が読みやすいでしょう。
そうすると,君が代起立斉唱事件について,どう考えるべきでしょうか。
やはり,相互承認を前提とするならば,不起立行為に対して不利益処分を背景に間接的に強制することは,これにより得られる利益との観点からも,正当化することが難しいのではないでしょうか。
我が国は,「ほぼ」単一国家であるため,「相互初認」よりも,「出る杭は打たれる」という観念が強いように思います。
私自身,伝統を重んじること,歴史に敬意を払うべきことには賛成しますが,「出る杭は打たれる」べきとは微塵も思いません。
「支障を是正するためにその限度で出る杭を打つことができる」というべきでしょうか。
長くてゴロが悪いですね。
第二次世界大戦の英霊に敬意を払うことも自由ですし,戦犯ゆえに崇めるべきではないと考えることも自由です。
公式参拝には議論があるところですが,少なくとも,靖国神社が存在する分にはかまわないわけです。
要するに,「憲法は,哲学なくして語れない」,ということです。
PR: マイクロソフト製品ダウンロードキャンペーン実施中
平成23年新司法試験の結果について
先程、法務省まで発表を確認しに行きました。
運良く合格することが出来ました。
読者の皆様の支えがなければ、ここまでがんばれませんでした。
本当にありがとうございました。
取り急ぎ、報告のみで失礼します。
iPhoneからの投稿
平成24年司法試験 公法系第1問
0 ごあいさつ
お久しぶりです。
春から梅雨へと季節が移り変わっているようですが,いかがお過ごしでしょうか。
司法試験を受験した皆様におかれましては,5日間という長丁場,本当にお疲れ様でした!
私自身が司法試験を受験し終わった平成23年5月15日。
この日は,借りていたマンションの契約満了日のため,引っ越しながらの受験でした笑。
しかし,2日目の民事系で大きなミスを自覚していたので,解放感よりも落胆の方が大きかったです。
翌日からは,しばらく不安で不安でたまらなかった記憶があります。
実家での引っ越しの荷ほどきをしながら,飲み会に参加し,バイトをする毎日でした。
合格発表まで勉強しよう!という意気込みは理解できますが,思う存分遊んでくださいね。
1 平成24年司法試験 公法系第1問
さて,本題に入りましょう。
再現答案を作成されている時期に,このような記事を書くのは精神的に打撃があるかも知れません。
しかし,私の記事が「正解」ではありません。1つの考え方です。
この記事と同じかどうかで一喜一憂するのは不毛です。あくまでも参考程度にお考えください。
今年の問題のテーマは,「政教分離」でした。
巷では噂されていたようですが,ドストレートな問題で,基礎力を試されるいい問題です。
(1)概要
A寺は,人口約1000人のB村の唯一の寺でした。B村の全世帯約300世帯のうち約200世帯がA寺の檀家であるC宗の末寺です。また,村民の交流の場であり,心理的ストレス相談も受け付けるなど,檀家以外の村民も日ごろから利用しています。
その上,B村には小規模な墓地は集落にあるのですが,大規模な墓地はA寺にしかありません。ところが,A寺は「宗旨・宗派は問わない」と記載するものの,実際にはC宗の規則で,他の宗旨・宗派の信者の場合,C宗の典礼方式で埋葬を行うことに同意した場合のみしか認めないとされていました。そのため,これに賛同できないDは,A寺の墓地に墓石を建立しませんでした。
なお,かつては一般的に当該寺院の宗旨・宗派の信者のみが墓石を建立できました。しかし,最近は,宗旨・宗派を一切問わない寺院墓地もあります。また,【参考資料】墓地,埋葬等に関する法律13条では,「墓地(略)の管理者は,埋葬,埋蔵(略)の求めを受けたときは,正当の理由がなければこれを拒んではならない。」と定めれられています。
ところが,山火事が発生し,本堂,庫裏(住職の住居)は全焼,墓地も物置小屋やひしゃく,卒塔婆が焼けてしまいました。なお,本堂に安置されていた観音菩薩像は無事でした。通常,寺院の再建には,檀家の寄付を募るのですが,山火事によりB村の主産業である林業関連の工場,会社も全焼してしまいました。さらに,A寺は火災保険に加入していなかったため,再建は困難でした。
そこで,B村村長は,全焼した村立小学校の再建を主目的とする補正予算審議において,A寺への再建助成をしたところ,①墓地整備に2500万円(必要費用の2分の1),②本堂再建に4000万円(同4分の1),③庫裏再建に1000万円(同2分の1)の助成が議決され,執行をしました。
このような状況で,Dは,今回のB村によるA寺への助成は憲法に違反するのではないかと思っています。
(2)形式面
本当に,政教分離真正面ですね。
今年も,平成23年に続き,訴訟選択を問われています。
地方自治法242条の2第1項4号に基づく不当利得返還請求の住民訴訟をすることになるでしょう。
なお,いわゆる宗教的人格権に基づく国家賠償請求(基本権訴訟)をすることは,自衛官合祀訴訟の趣旨に照らすと,難しいように思います。
設問2も,平成22年からのものを踏襲しています。
「設問1における憲法上の主張に関するあなた自身の見解を,被告側の反論を想定しつつ,述べなさい。」としているため,設問1の論評せよということですね。
2 設問1原告側の主張
(1)法的主張
まず,4号請求の中で,憲法89条前段,憲法20条1項後段違反を主張することになるでしょう。
本件は,純粋な公金支出行為であり,村長が宗教性の疑われる行為をしている事案ではありません。それゆえ,20条3項の「国及びその機関は,宗教教育その他いかならう宗教的活動もしてはならない。」という文言に違反するとはいいにくでしょう。
そこで,20条1項後段「いかなる宗教団体も,国から特権を受け,又は政治上の権力を行使してはならない。」,89条前段「公金その他公の財産は,宗教上の組織若しくは団体の使用,便益若しくは維持のため(略)これを支出し,又はその利用に供してはならない。」という条文に違反するかを問うべきでしょう。
そうすると,上記①~③の支出との関係で,C宗が「宗教上の組織」に該当するかを各々分析することになります。
ここで問題となるのは,政教分離違反の判断方法です。
愛媛玉ぐし料事件判決(最大判平9・4・2)は,「憲法の政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いを持つことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。」
このように,かつては,「原則中立,例外違憲」というスタンスでした。
ところが,砂川神社事件判決(最大判平22・1・20)は,「国家が宗教的に中立であることを要求」という文言を注意深く使用していません。
「国家と宗教とのかかわり合いには種々の形態があり,およそ国又は地方公共団体が宗教との一切の関係を持つことが許されないというものではなく,憲法89条も,公の財産の利用提供等における宗教とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,これを許さないとするものと解される。」としているのです。
このことは,後の白山ひめ神社事件判決(最判平22・7・22),第二次砂川神社事件判決(最判平24・2・16)も同様です。
そこで,この考えを進めて,「原則違憲,例外合憲」という図式で判断することを要請するべきでしょう。その際に参考になるのは,以下の個別意見です。
愛媛玉くし料事件判決
大野正男裁判官補足意見「公的機関が宗教にかかわりを持つ行為をすることによって、広く社会にこのような効果を及ぼすことは、公的機関を宗教的対立に巻き込むことになり、同時に宗教を世俗的対立に巻き込むことにもなるのであって、社会的儀礼や風俗として容認し得る範囲を超え、公的機関と宗教団体のいずれにとっても害をもたらすおそれを有するといわざるを得ない。そのようなことを避けることこそ、厳格な政教分離原則の規範を憲法が採用した趣旨に合致するものである。」
高橋久子裁判官意見「多数意見は、憲法のいう「国家と宗教との完全な分離」は理想であって、これを実現することは「不可能に近く」、これを完全に貫こうとすれば、「各方面に不合理な事態を生ずる」というが、果たしてそうであろうか。地鎮祭判決の挙げている不合理な事態の例は、特定宗教と関係のある私立学校への助成、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のための宗教団体に対する補助、刑務所等における教誨活動等であるが、これらについては、平等の原則からいって、当該団体を他団体と同様に取り扱うことが当然要請されるものであり、特定宗教と関係があることを理由に他団体に交付される助成金や補助金などが支給されないならば、むしろ、そのことが信教の自由に反する行為であるといわなければならない。」
「私も、「完全分離」が不可能あるいは不適当である場合が全くないと考えているわけではない。クリスマスツリーや門松のように習俗的行事化していることがだれの目にも明らかなものもないわけではなく、他にも同様の取扱いをする理由を有するケースが全くないと断定することはできない。しかし、「いかなる宗教的活動もしてはならない。」とする憲法二〇条三項の規定は、宗教とかかわり合いを持つすべての行為を原則として禁じていると解すべきであり、それに対して、当該行為を別扱いにするには、その理由を示すことが必要であると考える。すなわち、原則はあくまでも「国家はいかなる宗教的活動もしてはならない」のである。ところが、多数意見は、「国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いを持たざるを得ないことを前提とした上で」と、前提条件を逆転させている。」
尾崎行信裁判官意見「国家と宗教との完全分離を原則とし、完全分離が不可能であり、かつ、分離に固執すると不合理な結果を招く場合に限って、例外的に国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容されるとすべきものと考えるのである。
このような考え方に立てば、憲法二〇条三項が「いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定しているのも、国が宗教とのかかわり合いを持つ行為は、原則として禁止されるとした上で、ただ実際上国家と宗教との分離が不可能で、分離に固執すると不合理な結果を生ずる場合に限って、例外的に許容されるとするものであると解するのが相当である。したがって、国は、その施策を実施するための行為が宗教とのかかわり合いを持つものであるときには、まず禁じられた活動に当たるとしてこれを避け、宗教性のない代替手段が存しないかどうかを検討すべきである。そして、当該施策を他の手段でも実施することができるならば、国は、宗教的活動に当たると疑われる行為をすべきではない。しかし、宗教とのかかわり合いを持たない方法では、当該施策を実施することができず、これを放棄すると、社会生活上不合理な結果を生ずるときは、更に進んで、当該施策の目的や施策に含まれる法的価値、利益はいかなるものか、この価値はその行為を行うことにより信教の自由に及ぼす影響と比べて優越するものか、その程度はどれほどかなどを考慮しなければならない。施策を実施しない場合に他の重要な価値、特に憲法的価値の侵害が生ずることも、著しい社会的不合理の一場合である。こうした検証を経た上、政教分離原則の除外例として特に許容するに値する高度な法的利益が明白に認められない限り、国は、疑義ある活動に関与すべきではない。このような解釈こそが、憲法が政教分離規定を設けた前述の経緯や趣旨に最もよく合致し、文言にも忠実なものである上、合憲性の判断基準としても明確で疑義の少ないものということができる。そして、右の検討の結果、明確に例外的事情があるものと判断されない限り、その行為は禁止されると解するのが、制度の趣旨に沿うものと考える。」
これらの考え方,特に尾崎意見を参考に,原則違憲説を展開するべきでしょう。
(2)あてはめ
お楽しみに!
PR: 都道府県型JPドメイン名、登録受付中!
「憲法の流儀」連載開始のお知らせ
0.連載にあたって
お久しぶりです。
予告した通り、10月より「憲法の流儀」というタイトルの連載を開始します。
はじめに、私が連載にあたって考えたことを綴っておきたいと思います。
1.予備校の憲法がよくわからない
私は、司法試験受験生の頃、受験指導校に通っておりました。受験指導校の教育は、極めて合理的であり、ズボラな学生であった私には、手っ取り早く法律を理解するためには最適のツールでありました。実際問題として、学部の眠い授業よりも、予備校の講義は数倍わかりやすいという事実は否定できません。そのおかげで、何とか人並みの答案を書けるようになり、法科大学院の既修者コースに合格することができました。
司法試験の勉強においては、論点の実益について考えることが求められます。ところが、他の科目は考えればなるほど理解できるものの、憲法だけは考えすぎると筆が止まってしまいました。そこで、いわゆる予備校本に頼っても、一向に答えが出ませんでした。また、かの有名な芦部『憲法』を調べてみても、すべては行間という名の謎につつまれており、疑問を解消することは極めて困難でした。
そこで出会ったのが、当時「法学セミナー」で連載されていた、宍戸先生の『憲法 解釈論の応用と展開』でした。学部4年生だった私は、宍戸連載を何度も読み、憲法の奥の深さと面白さに圧倒され、いつしか研究論文を執筆したいという思いが強くなりました。
なお、宍戸連載は、内容が若干加筆されたものが単行本として出版されております。
憲法 解釈論の応用と展開 (法セミ LAW CLASS シリーズ )/日本評論社
¥2,835
Amazon.co.jp
2.「考え方」は1つじゃない
この連載では、受験指導校出身者である私の視点から、いわゆる予備校教育により陥りがちな間違った理解について指摘し、どう考えるべきかについて書いていこうと思います。ただし、連載で書いてある内容は、特に明示しない限り、私の独自説です。そのため、数ある考え方の1つにすぎないということを念頭に読み進めていただければ幸いです。
世の中には,「唯一絶対の正解」というものはありません。様々なあり得る考え方の中で,より説得的なものが,「一応の正解」であるにすぎないのです。何が「一応の正解」かは,自分自身で判断するしかありません。
憲法は,半分「法的」であり,半分「小論文的」でもあります。「法的」素養のためには,学説,判例を検討し,基本型を会得する必要があります。また、「小論文的」素養のためには,常に社会に目を向け、「考える」必要があります。
重要なのは、問題の核心を見抜き,考え,書くことです。司法試験は書面審査ですから、考えたことを答案に書かなければ,考えていない人と同じ評価になってしまいます。議論の中で大切なことは、見解を否定されても,人格を否定しているわけではないということです。過ちを犯したら,真摯に向き合い,次の糧にしてください。人間は,失敗して学ぶものですから。
それでは、長期連載となりますが、一緒に頑張りましょう。
予備校憲法に革命を!
伊藤たけるの講義「憲法の流儀小教室」はこちらから。

第1回 憲法訴訟の背後原理
第1章 憲法訴訟のルール
第1回 憲法訴訟の背後原理
何事も、物事の本質を理解するためには、背後原理を理解することが有益です。法律実務家を目指すみなさんが学習すべき憲法は、政治的な道具としての憲法解釈論ではなく、訴訟における憲法解釈論です。
憲法解釈論が登場する訴訟を「憲法訴訟」と呼ぶことにしましょう。では、憲法訴訟は、憲法上どのような位置づけにあるのでしょうか。
(1) 憲法訴訟は民主主義への介入
我が国の憲法は、民主主義を採用しています。すなわち、前文において「主権が国民に存することを宣言」し、1条において「主権の存する日本国民」と規定し、「全国民を代表する選挙された議員で組織」(43条1項))される両議院で構成される国会が、「国の唯一の立法機関である」(41条)と規定されています。その上で、「国会議員の中から国会の議決で」指名される内閣総理大臣(67条1項)及びその他の国務大臣で組織される内閣(66条1項)が、「法律を誠実に執行」(73条1号)すると規定されています。
さて、このような民主主義の下では、法律がおかしいと考えた場合、私達はどのようにするべきでしょうか。
ここで、「憲法訴訟を提起し、当該法律を違憲無効にする」という回答を考えた方は、活動家精神としては素晴らしいものがありますが、少し考え直してほしいところです。
法律がおかしいと考えた場合、民主主義の下では、民主制の過程で法改正を求めることが原則となります。
例えば、司法修習生に給料がなく、アルバイトも禁止であることがおかしいと思うなら、いきなり最高裁判所を相手取って、給費金支払請求訴訟を提起し、「司法修習生に対する給費制を廃止する裁判所法の一部を改正する法律は、憲法22条1項及び25条1項に反するものであり、違憲無効である」と意気込むより、もう一度、給費制を内容とする裁判所法の改正を世論に訴えかける方が先に行われるべきです。ビギナーズネットが1000人パレードというデモ行進をすることは、まさに原則通りに民主制の過程で給費制を実現しようとするものといえるでしょう。
そうすると、憲法訴訟はどのようなときに提起するのでしょうか。ここで、違憲審査権とは何かをもう一度考えてみましょう。憲法81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」と規定しております。すなわち、民主主義により決めた法律、民主主義に由来する命令、規則、処分について、憲法に適合しないものを違憲無効とすることができるのです。換言すれば、違憲審査権は、我が国が採用している原則である「民主主義を覆すもの」なのです。憲法訴訟は、民主主義という原則への介入であるということは、この連載の中で1番大切な背後原理ですので、しっかりと押さえておいてください。
(2) 司法消極主義
このように、憲法訴訟は、民主主義という原則への介入であるという考えに立てば、基本的には民主主義で解決するべきことになるため、例外となる憲法判断はむやみに行うべきではないという、司法消極主義を導くことができます。「憲法判断は事件の解決にとって必要な場合以外は行わない」という「必要性の原則」(芦部370頁)も、司法消極主義のあらわれとして説明することができます。
「必要性の原則」に基づいて準則化された一連のルールとして、「憲法判断回避の準則」(=ブランダイス・ルール)があります。その中でも特に重要なのは、「裁判所は憲法問題が記録上適切に提起されていても、もし事件を処理することができる他の理由が存在する場合には、その憲法問題には判断を下さない」というルール(第4準則)と、「議会の法律の効力が問題になった場合は、合憲性について重大な疑いが提起されても、裁判所が憲法問題を避けることができるような法律の解釈が可能かどうかを最初に確かめることは基本的な原則である」というルール(第7準則)でしょう(芦部370頁)。具体的には、合憲限定解釈や憲法適合解釈が可能ならば、それによるべきということになるでしょう。
なお、合憲限定解釈とは、「字義通りに解釈すれば違憲になるかも知れない広汎な法文の意味を限定し、違憲となる可能性を排除することによって、法令の効力を救済する解釈」(芦部371頁)を意味し、憲法適合解釈とは、複数の解釈がある場合、当該規定の文言、趣旨の他に、最高法規である憲法の保護する価値を体系の中に入れ込み解釈をする、体系的解釈の一種を意味します(宍戸305頁参照)。合憲限定解釈というには、「法令の文言、趣旨から最も素直な解釈を選んだら、当該規定が違憲的に適用される部分が出てきてしまうために、次善三善の解釈だけれども、やむを得ず違憲的部分を含まない解釈を選ぶという場面」であることが必要です(宍戸305頁)。
(3) 付随的審査制・違憲主張の適格・可分性の法理
また、民主主義への介入である違憲審査の範囲を限定的にする概念として、付随的審査制、違憲主張の適格、可分性の法理があります。
付随的審査制とは、「通常の裁判所が、具体的な争訟事件を裁判する際に、その前提として事件の解決に必要な限度で、適用法条の違憲審査を行う方式」(芦部368頁)をいいます。判例も、「憲法第81条は,米国憲法の解釈として樹立せられた違憲審査権を,明文をもって規定した」(刑訴応急措置法事件判決 最大判昭23・7・8刑集2-8-801)ものであり、「最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが,この権限は司法権の範囲内において行使されるもの」としております(警察予備隊訴訟判決 最大判昭27・10・8民集6-9-783【百選Ⅱ207】)。
また、芦部憲法に記載がないためか、平成20年度新司法試験の出題趣旨を契機に、ようやく受験生に認知されるようになった「違憲主張の適格」の議論も、違憲審査の範囲を制限するものといえます。
「違憲主張の適格」とは、訴訟当事者が、当該違憲主張をすることができるか、という論点です。「処分等によって憲法上の権利を直接に制限された者が、自己の憲法上の権利を援用して当該処分やその根拠法令の違憲を主張することは、当然に認められる」のですが、①「自己に直接適用される条項以外に、その法令中の他の条項あるいはその法令全体の違憲を主張し得るか」、②「第三者の憲法上の権利の援用が、どの範囲で許されるのか」という点が問題となります(作法216頁)。①は可分性の法理、②は(狭義の)違憲主張の適格という名前で呼ばれているものです(なお、①②の双方は、(広義の)違憲主張の適格の論点とされる場合が多いようです。作法、長谷部憲法等。)。これは、不必要な憲法判断を制限するための原理として位置づけることができます。
● まとめ
・憲法訴訟は、民主主義という統治の原則に対する例外である。
・例外であるから、極力、憲法判断は回避するべきである。具体的には、憲法適合解釈、合憲限定解釈を検討することで、法令違憲を回避することになる。
・例外であるから、違憲主張の適格も制限するべきである。具体的には、①可分性の法理、②(狭義の)違憲主張の適格が論点となる。
● 次回予告
第2回は「法令違憲と適用違憲」です。お楽しみに。
予備校憲法に革命を!
伊藤たけるの講義「憲法の流儀小教室」はこちらから。

※2012年11月4日一部変更 憲法の流儀 第2回 適用違憲と法令違憲
第2回 法令違憲と適用違憲
前回は、憲法訴訟の背後原理は、統治の原則である民主主義への介入である、ということを学習しました。今回は、憲法訴訟を提起する際、何を違憲と主張すべきかという、ターゲット設定について学習しましょう。
まず、憲法訴訟は、付随的審査制の下において、通常の民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟の中で憲法解釈論が問題となるものです。ですから、判例を読む際には、①民事・刑事・行政訴訟のいずれか、②民事・行政の場合は訴訟物は何か、という点を意識しましょう。予備試験や司法試験では、訴訟形態が問われますので、その対策としても必要な作業です。
訴訟法上適法に訴訟が提起された場合、一方当事者が、自己に有利な判決を導くために、自己に適用される条文や自己に対してなされた処分は違憲無効であると主張することになります。ここで、法令と処分、どちらをターゲットにするべきか、という問題が生じます。
(1) 適用違憲の議論は百家争鳴
平成20年新司法試験の採点実感等に関する意見2頁以下において指摘され、「法令違憲と適用違憲」の区別は、受験界で一台騒動になりました。学会でも、猿払事件の現代版である、いわゆる堀越事件二審判決(東京高判平22・3・29)が、猿払事件第一審判決(時國判決 旭川地判昭43・3・25判時514-20【百選Ⅱ215】)を彷彿させる「適用違憲」の手法を採用したことから、議論が活発に行われています。
※2-1堀越事件 社会保険庁職員による政党機関紙の配布が、国家公務員法110条1項19号及び102条1項の禁止する政治的活動に該当するとして起訴された事件。弁護団は、機械的事務を担当する国家公務員にまで、政治的活動の禁止をすることは、憲法21条1項に反すると主張している。
参考文献:法律時報増刊 国公法事件上告審と最高裁判所
法律時報増刊 国公法事件上告審と最高裁判所/日本評論社
¥2,900
Amazon.co.jp
法令違憲と適用違憲に関する学会での議論は、現在は百家争鳴状態です。このあたりについて詳細を書くことは控えますが、一部分では学会の共通了解が見受けられるようになりました。おそらく、山本龍彦先生の「適用審査と適用違憲」曽我部真裕先生他編『憲法論点教室』32頁以下(日本評論社・2012年)が、もっともよくまとまっていますので、ぜひ参照してください。
憲法論点教室/日本評論社
¥2,310
Amazon.co.jp
(2) 適用違憲3類型の確認
芦部先生は、適用違憲について以下の3つに分類しております。
第1類型(狭義の適用違憲)
合憲限定解釈が不可能である場合,すなわち合憲的に適用できる部分と違憲的に適用される可能性のある部分とが不可分の関係にある場合に,違憲的適用の場合をも含むような広い解釈に基づいて法令を適用するのは違憲である,という趣旨の判決。
第2類型(処分違法)
法令の合憲限定解釈が可能であるにもかかわらず,法令の執行者が合憲的適用の場合に限定する解釈を行わず,違憲的に適用した,その適用行為は違憲である,という趣旨の判決。
第3類型(狭義の処分違憲)
法令そのものは合憲でも,その執行者が人権を侵害するような形で解釈適用した場合に,その解釈適用行為が違憲である。
第1類型は、「法令を適用するのは違憲」とありますが、一般的には、処分(適用行為)ではなく法令を違憲とするものと解されています。換言すれば、一定の適用行為類型に関する部分違憲判決に等しいといえるでしょう。
第2類型は、処分(適用行為)を違憲とするものですが、通常の解釈によっては法令違憲となるものの、合憲限定解釈により法令を合憲した後、当該処分が限定解釈された要件の範囲内か否かを審査するものです。したがって、第1に法令審査により違憲部分が発見され、第2に合憲限定解釈をすることで法令を救済し、第3に当該処分が限定解釈された要件の範囲内かを審査するという手順になります。
近年、一般的に「処分違法」と呼ばれておりますが、要件解釈の際に憲法を参照する点で、単なる違法な解釈適用行為と異なることに注意が必要です。「違憲」ではなく「違法」とされているのは、「違法」として事案処理ができるならば「違憲」と宣言する必要性がないためであると考えられます。
第3類型も、処分(適用行為)を違憲とするものですが、ひとまず、法令審査を経ない純粋な処分審査の帰結であると理解しておけばよいでしょう。
(3) 司法試験における処分(適用)違憲 ※2012年11月4日変更
最高裁は、どうやら第1類型(狭義の適用違憲)は不要であると考えているようです。法令審査において違憲部分が発見された場合、適用違憲とせずに、当該違憲部分につき部分違憲判決をすることで足りるためでしょうか。
そうすると、司法試験における処分(適用)違憲とは、第2類型(処分違法)と第3類型(狭義の処分違憲)を意味すると解してよいでしょう。採点実感を注意深く読むと、平成20年では「法令違憲、適用(処分)違憲」(2頁)と表記されていましたが、平成23年には「法令違憲と処分(適用)違憲」(4頁)と表記されています。また、平成20年採点実感4頁は、法令違憲について「法令自体の問題点を論ずべき」として、適用違憲(処分違憲)について「当該処分(適用)の問題点を論ずる」もととしています。
この点から推察するに、法令と処分のどちらを対象に審査をしているか、という観点で、「法令違憲」と「処分(適用)違憲」を区別しているように見受けられます。
もっとも、司法試験との関係では、第1類型の審査をすることも否定はされていないようにも思えます。
例えば、要件解釈をすることが難しい場合は、第1類型で書く余地があります。
第1類型で論じる場合は、素直に司法事実を使って目的手段審査をすれば足ります。
(4) 具体的な審査方法
平成20年新司法試験の採点実感2頁によると、当事者としては,「法令違憲の主張をまず行い,それが認められない場合でも本件事件に関して適用違憲(処分違憲)が成り立つことを主張する方法が,まず検討されるべき」であるとされています。
※2-2 他方、同4頁では、「当該処分の違憲性から過度の広汎性等の理由で法令自体の違憲性へと進むアプローチもある」(=処分アプローチ)と紹介されていますが、推奨しません。このアプローチは、「適用審査優先原則」を採用する伝統的な学説の立場であり、最高裁判例とは異なるからです。また、処分アプローチ「も」あるとの表現から、そのアプローチでも採点はするけど、おすすめしないよ、というメッセージが読み取れるような気がします。なお、処分アプローチからは、法令に違憲部分がある場合、部分違憲ではなく、第1類型(狭義の適用違憲)による方が素直となります。芦部先生をはじめとする伝統的な見解が、第1類型(狭義の適用違憲)を紹介し、部分違憲を紹介しないのには、上記のようなアプローチに違いが関係しているように思います。
①何が違憲かを見極める
平成22年採点実感には、「必ず法令違憲と適用(処分)違憲の問題が両方存在するとは限らない」(1頁)との記載があります。これはまさしくその通りで、いったい何が違憲となるのかを見極めなければなりません。
特に、請求権(=国民が国家に対して何らかの作為を求めることができる権利)の場合、法令を違憲としてしまうと、給付等の国家の作為の根拠法がなくなってしまい、救済されなくなる可能性もあります。
②法令違憲の主張(=法令審査)をする
何が違憲かを見極め、法令違憲の主張(=法令審査)をすべきであると判断した場合、処分違憲の主張(=処分審査)に先だって法令審査をすることになります。
具体的な方法は、追って御紹介しますが、概ね目的手段審査、制度準拠審査をすることになるでしょう。
③合憲限定解釈を試みる
法令審査の結果として、ⅰ全部合憲、ⅱ違憲部分がある、ⅲ全部違憲の3つのパターンが考えられます。ⅰは合憲判決、ⅲは違憲判決をすればよいのですが、ⅱ違憲部分がある場合は一筋縄にはいきません。
この場合、司法消極主義(⇒第1回参照)の観点から、憲法判断回避の準則の第7準則より、まずは合憲限定解釈の可否を検討することになります(⇒第1回参照)。合憲限定解釈の要件は、少なくとも、ⅰその解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別されること、ⅱ合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合であることが必要であるとされます(札幌税関検査事件判決 最大判決昭和59・12・12民集38-12-1308参照)。
※2-3 なお、曽我部他『憲法論点教室』58頁(赤坂幸一先生執筆部分)は、合憲限定解釈要件として、札幌税関事件に倣い、上記ⅰ、ⅱに加え、ⅲ「一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない(最高裁昭和48年(あ)第910号同50年9月10日大法廷判決・刑集29巻8号489頁参照)」も必要であるかのように示唆しています。
しかし。この判例には「表現の自由を規制する法律の規定について」という限定があること、表現の自由に対する明確性を問題とした徳島市公安条例事件判決を参照していることから、当該判例の射程は表現の自由に限定されると解されます。したがって、徳島市公安条例事件判決の説示と同様である要件ⅲは、表現の自由の合憲限定解釈については必要ですが、その他の領域で必要か否かは別途検討が必要なはずです。私は、表現の自由の領域以外で、ⅲのように高度の明確性を要求する必要はないと考え、上位ⅰ、ⅱに限定しました。
④部分違憲判決を試みる
違憲部分があるものの、上記③で合憲限定解釈が不可能であれば、法令違憲判決をすることになります。法令違憲判決には、全部違憲判決、部分違憲判決(文言上、意味上)があります。
憲法判断回の準則からは、極力、部分違憲判決により違憲判断を小さくしたいところです。また、部分違憲判決は、法令の他の部分を有効とすることができるため、特に、受益的立法が違憲となっても、なお救済を求めることができるというメリットがあります。
ところが、部分違憲判決は、立法の書き換えに等しいため、立法権侵害のおそれがあります。したがって、部分違憲は,「立法者の合理的意思」に反しない場合にのみ許容されます。そのための考慮要素としては、「その法律全体の仕組み,当該規定が違憲とされた理由,結果の妥当性等」(国籍法判決今井裁判官補足意見参照)が挙げられます。
部分違憲判決が許されるとした場合、条文の文言の一部を削除することで対応できるならば、文言上の部分違憲判決をすることになります。この手法は、在外邦人選挙権判決(最大判平17・9・14民集59-7-2087)【百選Ⅱ160】、国籍法判決(最大判平20・6・4民集62-6-1367)【重判平20憲4】が採用しているものです。
他方、違憲部分に対応する文言がない場合、意味上の部分違憲判決をすることになります。「法○条の規定のうち、××としている部分は、憲法△条に違反し無効である」とするものです。この手法は、郵便法違憲判決(最大判平14・9・11民集56-7-1439)【百選Ⅱ139】が採用しているものです。
なお、部分違憲判決が立法者意思に反する場合、全部違憲判決をすることになるでしょう。
⑤処分違憲の主張(=処分審査)をする
このように、法令違憲、部分違憲、法令合憲と、法令に対する審査が終了したら、本件処分の効力がどうなるかを検討する必要があります。
法令違憲であれば、根拠法が消滅することになり、処分も当然に無効となります。他方、部分違憲であれば、当該処分が違憲部分を除去した法令の要件を満たしているかを検討することになります。また、法令合憲判決であっても、上記③で合憲限定解釈をしたのであれば、当該処分が限定解釈した要件に合致するかを審査する必要もあるでしょう。
このように、処分審査においてなすべきは、憲法に照らして法令の要件を解釈し、そこに事実をあてはめることであるといえるでしょう。ただし、根拠法令のない処分審査、例えば、政教分離が問題となる場合等は、法令の要件解釈とは異なる特別の審査が必要となります。
● まとめ
・適用違憲第1類型(狭義の適用違憲)は、司法試験との関係では不要。
・答案作成では、次の5つのステップを意識する。
①何が違憲かを見極める
②法令違憲の主張(=法令審査)をする
③合憲限定解釈を試みる
④部分違憲判決を試みる
⑤処分違憲の主張(=処分審査)をする
・必ずしも上記の5つのステップが全ての問題に妥当するわけではない。
● 次回予告
第3回は、「主張適格」です。お楽しみに。
予備校憲法に革命を!
伊藤たけるの講義「憲法の流儀小教室」はこちらから。

憲法の流儀 第3回「主張適格」
第3回 主張適格
さて、前回までは、憲法訴訟の背後原理、法令違憲と適用違憲の違いについて学習しました。これにより,どのような審査方法があり,具体的にはどのように審査をするのか,という点が,ぼんやりとわかっているはずです。
次のステップでは,「憲法上の主張は,どの範囲まで認められるのか?」という論点について学習しましょう。
ここで主張適格とは,違憲の争点を提起する適格という意味で使います。具体的には,「事件につき当事者適格のあるものが,攻撃又は防禦の方法として違憲の争点を提起する適格」のことをいいます(時國康夫『憲法訴訟とその判断の手法』203頁)。
その中でも,「第三者の権利の主張適格」は有名ですが,その背後には、特定の第三者と不特定の第三者を区別するという奥が深い議論が潜んでいます。また,仮に自己の権利であっても,あらゆる憲法上の主張が認められるわけではありません。具体的には,本件で適用されている法律のうち,適用されていない条項についての違憲性を主張できるかは論点です。これは,「可分性の法理」といわれるものです。
実は,主張適格については様々な文献があるのですが,芦部憲法には記載がありません。現時点では,長谷部414頁以下が一番よくまとまっていますので,一読をお薦めします。
(1) 原則は「自己の権利が,直接,現在」制約されている場合
まず,主張適格が認められるのは,原則として,「自己の権利が,直接,現在」制約されている場合に限られます。
その理由は,次の2つに求められるでしょう。第1に,憲法訴訟は民主主義の例外であるという司法消極主義より,違憲審の範囲は極力限定するべきこと(⇒第1回参照),第2に,他人の権利や将来侵害される権利については,適切な訴訟追行が期待できないことです。後者については,民事訴訟法の当事者適格の議論でも,同様の論証がありましたね。
(2) 例外その1:特定の第三者の権利の主張適格
これに対する例外として,①特定の第三者の権利の主張適格,②不特定の第三者の権利の主張適格の2つがあります。
特定の第三者の権利の主張適格とは,当該処分により,現実に特定の第三者の権利が侵害されているような場合,当事者がこれを援用できるか,という問題です。他方,不特定の第三者の権利の主張適格とは,具体的に特定の第三者の権利が侵害されているとはいえないが,観念上の第三者や,将来侵害されるであろう第三者の権利について,具体的な権利侵害が発生する前に当事者が援用できるか,という問題です。
この2つはしっかり区別しておいてください。平成23年出題趣旨1頁も,「ユーザーは不特定多数の第三者であるので,特定の第三者に関する判例を根拠にX社がユーザーの「知る自由」を理由に違憲主張できるとするのは,不適切であり,不十分である。」として,しっかり区別しなさいとのメッセージを発信しています。
特定の第三者の権利の援用は,①司法消極主義及び②適切な訴訟追行の確保の観点から,原則として認められません。例外的に認められるのは,これらの趣旨が妥当しない場合,換言すれば,①司法消極主義であるべきではない場合,②適切な訴訟追行が期待できる場合でしょう。
すなわち,ⅰ萎縮効果を早期に除去する必要がある場合や,ⅱ第三者が独立に自己の憲法上の権利侵害を主張する実際的可能性(後訴提起可能性)がない場合は,①司法消極主義は妥当しません。なぜなら,ⅰ萎縮効果が既に発生しているのであれば,現に適法な表現行為が差し控えられており,民主主義の過程そのものに瑕疵があるのですから,瑕疵ある民主主義を尊重する理由はありません。また,ⅱ第三者の後訴提起可能性がないのであれば,当該論点は,将来問題になることはありませんから,現在争う実益があるといえます。
また,ⅲ当事者の訴訟における利益の程度が強い場合や,ⅳ援用者と第三者との関係(人的関係)が密接な場合,②適切な訴訟追行を期待することができます。すなわち,ⅲ訴訟に利益があるならば,当然当事者は自己に有利な判決を求めるでしょうし,ⅳ人的関係が密接な場合も同様でしょう。
このように,「当事者の訴訟における利益の程度,援用される憲法上の権利の性質,援用者と第三者との関係,第三者が独立に自己の憲法上の権利侵害を主張する実際的可能性」を考慮して,総合的に判断することになるでしょう(芦部『憲法訴訟の理論』,読本318頁参照)※3-1。学説は,特に後訴提起可能性を重視しているようです(大石和彦「争点」278頁)。
この点については,◆3-1【判例を読む】第三者所有物没収事件を読んで,理解を深めてください。
※3-1 オウム真理教解散命令抗告審決定(東京高決平7・12・19判時1548-26)も,宗教団体が信者の信教の自由を援用できるかに関して,類似の枠組みを採用している。が,同事件の最高裁決定(最決平8・1・30民集50-1-199)【百選Ⅰ42】は,主張適格につき論点として扱わず,信者の信教の自由を考慮している。
(3) 例外その2:不特定の第三者の主張適格
これに対して,不特定の第三者の権利の主張適格の場合,特定の第三者と異なり,個別具体的な関係を検討することは難しいでしょう。
そのためか,これが認められるのは,萎縮効果を早期に除去する必要があるという,別の理由が用いられます。
実は,この理論こそが,かの有名な「過度の広汎性ゆえに無効の法理」と呼ばれるものなのです。「過度の広汎性ゆえに無効の法理」とは,「法文は一応明確でも,規制の範囲があまりにも広汎で違憲的に適用される可能性のある法令も,その存在自体が表現の自由に重大な脅威を与える点で,不明確な法規の場合と異ならない」として,「合理的な限定解釈(それには厳格な枠がある)によって法文の漠然不明確性が除去されないかぎり,かりに当該法規の合憲的適用の範囲内にあると解される行為が争われるケースでも,原則として法規それ自体が違憲無効(文面上無効)となる」と紹介されています(芦部197頁)。
つまり,「当事者との関係では合憲であっても,誰かさんとの関係では違憲になるような過度に広汎な立法である場合,全体として違憲無効だから,当事者は救済されます」という意味があります。具体的には,広島市暴走族追放条例事件を例にすると,「暴走族である被告人Xとの関係では合憲だが,同条例の処罰範囲に,ゴールデンボンバーのコスプレをして『女々しくて』のダンスを踊る不特定のYの行為まで含まれる可能性があるため,条例全体が違憲である」という主張が許されることになります。
正直,かなり難しいことを書いているので,◆3-2【判例を読む】広島市暴走族追放条例事件を読んで理解を深めてください。
(4) 例外の例外:可分性の法理
もっとも,第三者の主張的が認められたとしても,そこで安心してはいけません。主張適格が認められるためには,その上で,可分性の法理をクリアする必要があります。
可分性の法理とは,当該処分の根拠条文(=適用条項)とは異なる条文の文言,条文又は法令の憲法適合性が問題となっている場合,問題となる条文が可分であれば,当該条文が違憲であると主張する適格を認めないというものです。その理由は,もちろん司法消極主義にあります。すなわち,問題となる条文が違憲であるとしても,当該条文のみが違憲となっても,処分の根拠条文は残存するため,当該条文に対する憲法適合性の審査は無意味です。
ですから,適用条項と異なる条文が違憲であるとの主張をするためには,当該条文がなくなれば法律が全体として無効になる場合や,少なくとも適用条項も違憲となるような場合でなければなりません。
その判断基準は,「法律の違憲的な部分が除去されてしまえば,議会は残りの有効な部分のみだけでは満足しなかったであろう蓋然性が明白か否か」によります(芦部『憲法訴訟の理論』(有斐閣・1973年)172~173頁)。
なお,可分性の法理は,たとえ萎縮効果により広く主張適格が認められても,これを制限するように働く点に注意が必要です。このあたりも,◆3-3【判例を読む】札幌税関事件にて、同事件が審査した範囲を学習すると,より明確にイメージがつかめるでしょう。
● まとめ
・主張適格は「自己の権利が,直接,現在」制約されている場合に認められるのが原則
・主張適格が制限される趣旨は,①司法消極主義,②適切な訴訟通行を期待できないこと
・例外その1:特定の第三者の権利の主張適格は,以下の4要素を検討する。
ⅰ萎縮効果を早期に除去する必要がある場合
ⅱ第三者が独立に自己の憲法上の権利侵害を主張する実際的可能性(後訴提起可能性)がない場合
ⅲ当事者の訴訟における利益の程度が強い場合
ⅳ援用者と第三者との関係(人的関係)が密接な場合
上記ⅰⅱは趣旨①が,ⅲⅳは趣旨②が妥当しない。
・例外その2:不特定の第三者の権利の主張適格は,委縮効果を除去する必要性がある場合に認められる(過度の広汎性ゆえに無効の法理)。
・例外の例外:適用条項と異なる条文が違憲であるとの主張をするためには,当該条文がなくなれば法律が全体として無効になる場合や,少なくとも適用条項も違憲となるような場合でなければならない(過分性の法理)。
● 次回予告
第4回は「違憲審査基準論」です。お楽しみに。
予備校憲法に革命を!
伊藤たけるの講義「憲法の流儀小教室」はこちらから。

【速報】堀越事件上告審判決・解説
0 堀越事件とは
平成24年12月7日,最高裁第二小法廷は,堀越事件につき無罪の判断をした高裁判決(東京高判平22・3・29)(=中山判決)に対する検察官の上告を棄却し,堀越氏の無罪が確定しました。
判決文はこちら
堀越事件について,ご存じでない方も多いと思いますので,軽く解説しておきましょう。
ロースクールの教授の中には,当然学生も知っていると思っている方がいらっしゃいますので,授業で取り扱われるかもしれませんね。
堀越事件とは,猿払事件(最大判昭49・11・6刑集28-9-393)【百選Ⅰ15】の再来といわれる,憲法学者大注目の事件でした。
問題となったのは,猿払事件と同様,公務員の政治活動の自由です。
具体的には,国家公務員の政治的活動を一律に禁止する国家公務員法102条1項,その委任を受けた人事院規則14-7(政治的行為)6項7号,13号(5項3号)の憲法適合性が問題となりました。
猿払事件では,第1審判決(旭川地判昭43・3・25下刑集10-3-293)【百選Ⅱ215】(=時國判決)が,いわゆる適用違憲第一類型の手法を採用し,無罪判決を言い渡しました(百選解説,芦部376~377頁参照)。
しかし,第2審でも無罪となったにもかかわらず,最高裁は,大法廷判決において,有罪判決を下しました。
この時の最高裁長官は,村上朝一裁判官であり,「村上コート」と呼ばれておりました。
村上コートの前は,全農林警職法事件において,保守的な判例変更をした石田コートでした。
村上コートは,石田コートの保守派の雰囲気を承継したものでありました。
このあたりは,山田隆司著『最高裁の違憲判決―「伝家の宝刀」をなぜ抜かないのか』(光文社新書,2012年)106頁以下が参考になります。
なお,猿払事件の調査官の香城敏麿裁判官も,著名な裁判官ですので,名前を憶えておいて損はないでしょう。
堀越事件も,国家公務員の政治的活動の自由が問題になった点のみならず,第2審では適用違憲の手法を用いて無罪判決がなされた点でも,猿払事件を彷彿させるものがあります。
そこで,最高裁に係属したところ,判例が変更される場合になされるはずの口頭弁論がなかったため,最高裁の無罪判決が期待されておりました。
しかし,無罪判決をするには,猿払事件判決を判例変更しなければならないはずです。
ところが,判例変更をするためは大法廷で判断しなければならないのですが,大法廷回付はなされませんでした。
そこで,判例変更によらず,どのような無罪判決がなされるのか注目されていたわけです。
1 事案の概要
堀越氏は,社会保険庁東京都社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官として勤務していた厚生労働事務官でしたが,共産党を支持する目的をもって,機関紙のしんぶん赤旗等を配布したため,国公法違反で起訴されました。
2 多数意見
(1) 法令の処罰対象の限定
まず,立法目的を行政の中立的運営の確保,対立利益を表現の自由に特定しました。
その上で,ⅰ法の文言,趣旨,目的,ⅱ規制される政治活動の自由の重要性,ⅲ刑罰法規の構成要件となることを考慮し,処罰対象である「政治的行為」につき「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが,観念的なものにとどまらず,現実に起こり得るものとして実質的に認められるもの」として,その委任をうけた人事院規則に対しても同様の解釈をしました。
具体的には,ⅰ人事院規則が定める行為類型に文言上該当する行為であって,ⅱ公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるもの,を当該各号の禁止の対象となる政治的行為と規定したものと解しました。
そして,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは,公務員の地位,その職務の内容や権限等,当該公務員がした行為の性質,態様,目的,内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である,という判断材料を示しました。
(2) 限定部分した条文に対する憲法適合性審査
上記のように,同法の適用範囲を限定した上で,憲法適合性を審査します。
基本的には猿払をなぞっているのですが,「禁止の対象とされるものは,公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治的行為に限られる」として,必要かつ合理的な範囲と結論付けている点,間接的・付随的規制論が抜け落ちている点で異なりますね。
(3) 限定した構成要件に該当するかを審査
その後,「本件配布行為が本件罰則規定の構成要件に該当するか」を検討して,「管理職的地位にはなく」「裁量の余地のない」等を理由に「構成要件に該当しない」として無罪であると判断しました。
(4) 適用違憲は採用しない(第2審判決への批判)
なお書きにおいて,「原判決は,本件罰則規定を被告人に適用することが憲法21条1項,31条に違反するとしているが,そもそも本件配布行為は本件罰則規定の解釈上その構成要件に該当しないためその適用がない」として「原判決中その旨を説示する部分は相当ではない」と批判していますね。
(5) 猿払事件との整合性
最後に,原判決の猿払事件違反について,猿払事件は「労働組合協議会の決定に従って(中略)構成員である職員団体の活動の一環として行われ,公務員により組織される団体の活動としての性格を有する」構成要件に該当する行為であるから,「事案を異にする」として,同判決と矛盾・抵触はないと結論づけております。
3 千葉勝美裁判官の補足意見
(1) 猿払事件と矛盾はない
千葉補足意見は,猿払事件との整合性につき,「判決による司法判断は,全て具体的な事実を前提にしてそれに法を適用して事件を処理するために,更にはそれに必要な限度で法令解釈を展開するものであり,常に採用する法理論ないし解釈の全体像を示しているとは限らない」と説いております。
そのため,「猿払事件大法廷判決の上記判示は,本件罰則規定自体の抽象的な法令解釈について述べたものではなく,当該事案に対する具体的な当てはめを述べたもの」として,猿払事件の判例の射程は,他の事件に及ぶものではないと説きます。
したがって,「本件罰則規定の法令解釈において本件多数意見と猿払事件大法廷判決の説示とが矛盾・抵触するようなものではない」と結論付けております。
この点は疑問ですね。
法令審査は当該具体的事実の範囲に限られるという見解は,結局適用違憲と同じではないでしょうか。
強いて違いがあるとすれば,土井先生の分類による違いと似ているように思います(ジュリ1400号51頁以下)。
すなわち,土井説の分類によると,典型的な適用違憲は「適用事実審査」,千葉補足意見は「法令適用審査」に該当するため,たしかに別物ではあります
しかし,土井説は双方を「適用審査」と位置付けるため,千葉補足意見の立場であっても,千葉意見が適用違憲の問題点として指摘する明確性の問題があるように思います。
(2) いわゆる合憲限定解釈やブランダイス・ルールではない
また,千葉補足意見は,本件の限定した解釈につき,「いわゆる合憲限定解釈の手法(中略)を採用したというものではない」と説きます。
そうではなく,本件は,「憲法の趣旨を十分に踏まえた」上で,「条文の丁寧な解釈」を試みたものであるにすぎないというのです。
さらに,この解釈はブランダイス・ルール(=憲法判断回避の準則)でもないという。
その理由として,司法の自己抑制を理由とする同準則と異なり,この手法は「通常の法令解釈の手法によるもの」にすぎないことを挙げています。
(3) 適用違憲は曖昧だからダメ
最後に,高裁の適用違憲判決(中山判決)につき,「表現の自由の規制立法の合憲性審査に際し,このような適用違憲の手法を採用することは,個々の事案や判断主体によって,違憲,合憲の結論が変わり得るものであるため,その規制範囲が曖昧となり,恣意的な適用のおそれも生じかねず,この手法では表現の自由に対する威嚇効果がなお大きく残る」として,適用違憲を否定しています。
しかし,上記(1)で指摘したように,千葉補足意見のように,法令審査は当該事実類型の限度でのみの部分的な判断であるかのような立場も,同じように明確性の問題を抱えていると思います。
3 須藤意見
(1) 刑罰の特殊性を強調
これに対し,須藤裁判官意見においては,「刑罰は国権の作用によるもっとも峻厳な制裁」であるから「処罰の対象とすることは極力謙抑的,補充的であるべき」として,刑罰が強力な制限であることが強調されています。
その上で,保護法益を
ⅰ行政の中立的運営
ⅱこれに対する信頼
に分け,ⅱ信頼のみが失われた場合は刑罰は許されず,懲戒処分が適切であると説きます。
他方,刑罰は,ⅰ行政の中立的運営が実質的に害される場合に限定されるとして,しょばんつ範囲をさらに限定します。
(2) 一つの限定解釈といえなくもない
さらに,本件は合憲限定解釈ではないとする千葉補足意見に対し,「一つの限定解釈といえなくもない」とした上で,合憲限定解釈要件につき検討しています。
具体的には,
ⅰ「規制の対象となるものとそうでないものとを明確に区別できないわけではない」
ⅱ「一般の国民にとって具体的な場合に規制の対象となるかどうかを判断する基準を本件罰則規定から読み取ることができるといえる」(札幌税関事件参照)
として,合憲限定解釈要件を満たさなくもない,と判断しております。
(3) 限定解釈は明確性の観点から問題がある
もっとも,「上記のような限定解釈は,素直なところ,分離を相当に絞り込んだ面があることは否定できない」として,やっぱり無理あるよね,と自白しています。
これに加えて,
ⅰ本法及び規則には「文理上広汎かつ不明確」ゆえ「委縮的効果が生じるおそれがあるとの批判がある」こと
ⅱ犯罪構成要件を人事院規則に委任している点が憲法21条,31条等に違反するとの見解(猿払事件・大隅ら4裁判官反対意見)があること
を指摘し,「更なる明確化やあるべき規制範囲・制裁手段について立法的措置を含めて広く国民の間で一層の議論が行われてよい」と結論づけています。
4 本判決の評価
(1) 総評
本判決は,国家公務員の政治的行為に対する刑罰の範囲につき,「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるもの」という限定解釈をした点は,素直に評価できます。
しかし,猿払事件と抵触しない,というロジックは極めて疑問ですね。
大法廷に回さないで,堀越事件を無罪にするための「オトナの判断」があったように感じます。
(2) 合憲限定解釈ではない?
ところで,本判決の多数意見は,札幌税関事件の合憲限定解釈要件にあてはめていません。
これは,広島市暴走族追放条例事件判決の同様でした。
本判決が,暴走族事件と同様,合憲限定解釈であることの判断を避けたのは,須藤意見に見られるように,「ぶっちゃけ合憲限定解釈は無理がある」との指摘を回避したかったから,と考えることもできますね。
実際に「実質的に認められる」という要件を合憲限定解釈で導くのは,明確性の観点から無理があるように感じます。
(3) 憲法適合性審査が骨抜きでは?
それでは,本判決の解釈手法は,いったい何なのでしょうか?
本判決のロジックは,
ⅰ法102条1項につき,「規制される政治活動の自由の重要性」を加味して,構成要件を限定解釈
↓
ⅱ限定した部分につき憲法適合性を審査して合憲
という構造になっています。
しかし,これでは結局ⅰの審査で違憲部分を除去してるわけで,本来厚く審査すべきである憲法適合性を論じるはずのⅱでは,キチンと審査していないように感じます。
これでは「憲法適合性」の判断では何も審査していないに等しく,審査が骨抜きになっていると評価せざるを得ません。
ぶっちゃけると,答案ではあまり参考にならない手法のように感じています。
(3) 猿払事件と抵触しないの?
また,私は,猿払事件と抵触するように感じております。
ア 理論的な抵触がある
猿払事件は,いわゆる「くさったミカンの理論」を採用し,一公務員の行為であっても,その弊害を軽く見るべきではないと判示しておりました。
「特定の政治的行為を行う者が一地方の一公務員に限られ、ために右にいう弊害が一見軽微なものであるとしても、特に国家公務員については、その所属する行政組織の機構の多くは広範囲にわたるものであるから、そのような行為が累積されることによつて現出する事態を軽視し、その弊害を過小に評価することがあつてはならない。」
この「くさったミカンの理論」によると,観念的に害するおそれがある行為も,積み重なれば問題となるとして,処罰の対象であったように解することもできます。
しかし,本判決は,実質的に害する行為のみを処罰の対象とするように,限定した解釈を展開しております。
イ 判決の効果は具体的事実にとどまらない
また,上記で指摘した通り,千葉補足意見が前提とする,法令審査は当該具体的事実の範囲に限られるという見解は,結局適用違憲と同じではないかという疑問があります。
したがって,法令違憲の範囲は,当該事例にとどめるべきでなく,広く同法が問題とされる事案にも及ぶと解するべきでしょう。
5 おわりに
Twitterの発言をベースに,切った貼ったしてみました。
とりとめのない内容ですので,後日修正したいと思います。
取り急ぎ,ご報告まで。
PR: So-net モバイル WiMAX
答練の必要性~予備校とLSの狭間で①~
1 司法試験の勉強法の書籍が少ない
そういえば,最近は,司法試験合格者による勉強法の書籍を見かけなくなりましたね。
私が勉強を開始した2006年2月頃は,まだまだ旧司法試験がメインの時代でしたので,この類の書籍にはお世話になりました。
現在はブログ等を通じて,勉強法の情報を集めることもできるかもしれませんが,有益なブログをウェブ上から探すのは簡単ではありません。
また,そもそもネットサーフィンをしないような方もいらっしゃるので,書籍には別のマーケットがあるように思います。
予備試験はさておき,法科大学院生においては,「予備校との距離の取り方をどうするか?」が典型論点のように,それなりの需要はあるのではないかと思います。
2 予備校の合格体験記は宣伝材料
勉強法なんて,予備校の合格体験記を読めばわかるでしょ?と言われそうですが,果たしてそうなのでしょうか。
予備校の合格体験記は,大学やLSの生協,予備校の入り口付近で,無料で配布していますね。
それも大量に。
このことは何を意味するか考えてみましょう。
そうです。
合格体験記は,予備校の商品を売るための広告の1つにすぎません。
ですから,合格体験記を寄稿したところで,都合の悪い記載は削除されますし,他の予備校については文言をぼかして活用されます。
それが悪いとは思いませんが,そのような「しがらみ」があることを把握したうえで,情報に接することが大切ですね。
3 論文答練は必要
では,法科大学院に通学したら,予備校は不要なのでしょうか。
答えは,NOです。
実際,私も予備校の答練や全国模試を活用していました。
むしろ,私は師匠に,「論文答練だけは受けろ」と口を酸っぱくして言われた記憶があります。
若い読者の方々はご存じないかもしれませんが,私の母校である慶應義塾大学法科大学院は,某教員の問題漏えい疑惑があった関係で,学内における答案指導は禁止されています。
他の法科大学院は知りませんが,私が在籍していた平成21年4月~平成23年3月まで,法科大学院生向けの添削は一切ありませんでした。
ただし,司法試験では,当然のことながら答案を書けなければ合格できません。
答案を書けるようになるためには,とにかく日頃から「書くこと」を意識する必要があります。
また,友達との答案検討だけでは不十分です。
司法試験が相対評価で合格が決まることを考えると,受験生の中で自分がどの位置にいるのかを把握する必要があります。
ですから,答練の順位を一応気にする必要があります。
もちろん,たかが答練ですので,順位がいいからといって油断してはいけません。
反対に,順位がクズだった場合,必ず何かの問題点がありますので,猛省してください。
以上のように,①定期的に書く練習をすること,②自分の相対的な位置を知ることができることから,答練は必要であるといえるでしょう。
なお,択一答練は時間の無駄です。
セットで安くても,全国模試以外を受ける必要性は乏しいでしょう。
択一対策については,過去の記事を参照してください。
4 答練の受講時期,受講形態
(1)受講時期はお早目に
答練を開始する時期ですが,早いに越したことはありません。
私は,新司法試験の問題を法科大学院2年生の9月より毎週1科目書いていましたので,答練自体を受講したのは法科大学院3年生の9月です。
(2)団体割引を活用すべし
団体割引等がありますので,お友達と一緒に申し込みをすると,かなり安くなります。
場合によっては,営業次第では,肢別本をプレゼント!なんてこともあるようです。
(3)可能な限り通学で
地理的要因もあるとは思いますが,可能な限り通学で受講してください。
インターネットですと,いつでも受講できる反面,強制力に乏しいです。
何よりも,自分に厳しく受講でします。
答練は,「まだちゃんと予習してないからあとでにしよう」ということはできますが,司法試験は容赦なく5月に訪れます。
答練の準備など,むしろする必要はありません。
答練でも,本番同様,よくわからないところからスタートする練習をするべきでしょう。
また,通学はお友達と一緒にすることを推奨します。
当該問題を題材に,お友達と議論をすることで,実力はかなり深まりますから。
要するに,団体割引を使って,お友達と一緒に通学する方法が一番おすすめということです。
5 各予備校の特徴
私は,法科大学院入試までは伊藤塾のコンプリート論文答練を受講しておりました。
また,新司法試験との関係では,辰巳のスタ論と全国模試,伊藤塾の全国模試を受講しておりました。
その関係で,双方の特徴については,それなりに知っておりますので,以下,簡単にご紹介したいと思います。
(1)辰巳の特徴
○長所
・解説が秀逸な講師がいる(特に,公法は加藤晋介先生,中尾隆宏先生,民事は山本和敏先生,刑事は菊地幸夫先生,新庄健二先生)
・事実を細かくピックアップする癖がつく
・採点基準が複数の考え方を想定している
・母集団が多い
○短所
・問題が重要判例の焼き増し(通称:重判答練)
・解説がアレな講師がいる(特に……続きはメッセージにてお問い合わせください笑。)
・とりあえず事実を挙げると点数がとれてしまう
○こんな人におすすめ
・事実を拾う癖のない人
・重要判例をきちんと理解していない人
・裁判官や検察官出身の視点を知りたい人
(2)伊藤塾の特徴
○長所
・最新論点を扱う秀逸な問題
・疑問点を書けば回答してくれるTWO-WAY添削
・上位LSの学生が多い印象がある
○短所
・採点基準があいまいなため「読みやすさ」で点が決まることも
・答案例以外の考え方は評価されにくい
・講師は純粋な弁護士のみで裁判官,検察官出身がいない
○こんな人におすすめ
・答案が読みにくいと言われている人
・最新の論点を自分の頭で考えてみたい人
・イケてるLS生と情報交換したい人

(3)その他
私から評価することはできませんが,LECやWセミナーにも答練はあります。
詳細は以下のリンクを参照してください。
LEC↓

Wセミナー↓
6 まとめ
長々と書いてしまいましたが,予備校が不要であるとは毛頭思いません。
ただ,「それだけ」で勉強するというのには無理がある,ということにすぎません。
何事も,適切な距離を保つことが重要ですね。
PR: 広告・Webの求人情報・転職支援はマスメディアン
第4回 違憲審査基準論※2013年1月5日一部追加
前回までは,憲法訴訟の背後原理に始まり,法令審査と適用審査という道具を習得し,主張適格というルールを学びました。
今回は,いよいよ「違憲審査基準論」の中身に入っていきます。
みなさんには馴染み深いようで,正直なところハッキリとは理解できない部分ですよね。
様々な見解があるところですが,司法試験の出題趣旨に依拠して説明していきますので,ご安心ください。
1 違憲審査基準論とは(芦部102~103頁)
平成22年採点実感2頁では,「審査基準とは何であるのかを,まず理解する必要」があると述べられています。
そこで,違憲審査基準論につき,もう一度芦部憲法を読み直してみましょう。
なお,違憲審査基準論は,いわゆる適用審査においても,基本的には妥当します。
(1)公共の福祉による制限の時代
まず,かつての判例は,①「公共の福祉という抽象的な原理によって人権制限の合憲性を判定する考え方」でした。
すなわち,憲法改正直後の判例は,特に理由もなく「公共の福祉に反しない」と結論付けて,合憲の判断をしておりました。
そのため,学説では「公共の福祉」の定義が争点となりました。
すなわち,「公共の福祉」につき,人権に外在する公益を意味すると解する見解(一元的外在的制約説)によると,およそ公益に資するのであれば「公共の福祉」に反しないとして,合憲の法律が多くなるでしょう。
他方,人権相互の矛盾衝突を調整する実質的公平の原理であるとする見解(一元的内在的制約説)によると,当該規制立法が,他の人権を保障するものか否かを審査する必要が生じます。
このように,かつては「公共の福祉=人権制約根拠+合憲性を審査する道具」という図式で理解されていました。
(2) 個別的利益衡量の時代
しかし,「公共の福祉」の定義という抽象的なものだけで,合憲性を判定することには無理があります。
そこで,「公共の福祉」は,人権を制約する根拠ではあるが,合憲性の判定にあたっては,抽象的な審査ではなく,得られる利益と失われる利益を比較衡量して検討するべきであろう,という②個別的利益衡量(ad hoc balancing)の考え方が登場しました。
この考え方は,「公共の福祉=人権制約根拠」,「個別的利益衡量=合憲性を審査する道具」という棲み分けをしているわけです。
この考え方は,次第に判例にも受け入れられるようになりました。
もっとも,個別的利益衡量は,「一般的に比較の準則が必ずしも明確ではなく,とくに国家権力と国民との利益の衡量が行われる憲法の分野においては,概して国家権力が優先する可能性が高い」という問題点があります。
すなわち,利益と利益は質が異なるため,本来は比較が困難であるところ,国家権力である裁判所が判断することになるから,国家に有利な判断になるおそれがある,というわけです。
例えば,卒業式を荘厳な雰囲気で行う利益と教員の一部が国歌を起立斉唱することで失われる内心の自由は,一概に比較することはできません。
まるで,サッカーの本田圭佑選手と野球のイチロー選手はどっちが強いの?という問いに近いものがあります。
このような場合に,国家に有利なように土俵を設定するおそれがある,というわけです。
すなわち,仮に裁判官がイチロー好きなら野球で,裁判官が本田好きならサッカーで勝負することになるでしょう。
しかし,これでは裁判官による恣意的な判断のおそれがあるわけです。
(3) 審査基準論の登場
そこで,裁判官の思考過程を拘束するツールとして,「一元的内在的制約説の趣旨を具体的な違憲審査基準として準則化」した違憲審査基準論(「二重の基準」の理論とも呼ばれます。)が登場したのです。
このように,違憲審査基準論とは,裁判官の思考を拘束するルールなのです。
すなわち,合憲と判断するためには,どのような条件が必要か,ということをあらかじめ定めておき,具体的な事例において,その条件を満たしているかを審査するわけです。
そして,その合憲と判断するための条件が,審査基準の強弱(=審査密度)で変化するのです。
このイメージは,めちゃくちゃ大切なので,しっかりと押さえておきましょう。
なお,木村草太先生のブログの記事に素晴らしい解説がありますので,そちらもご参照ください(2013年1月5日追加)。
(4) 表現の自由VSプライバシー権=個別的利益衡量という考え方
なお,予備校答案では,重要な権利と重要な権利を調整する場合には,個別的利益衡量にする,という論証を見かけます。特に,表現の自由VSプライバシー権の調整問題の答案で見かけますね。
これは,芦部憲法102頁にある,「この基準(注:個別的利益衡量のこと)は,同じ程度に重要な2つの人権(たとえば,報道の自由とプライバシー権)を調整するため,裁判所が仲裁者としてはたらくような場合に原則として限定して用いるのが妥当であろう」という記述に依拠しているのでしょう。
たしかに,「同じ程度に重要な2つの人権」の調整の場合には,個別的利益衡量と書いてあるようにも読めますが,個別的利益衡量は裁判官の恣意的判断を防止できないという欠点があるという文脈を考慮すると,ここでの力点は「裁判所が仲裁者としてはたらくような場合」にあると考えるべきでしょう(宍戸31~32頁参照)。
したがって,平成23年新司法試験のように,表現の自由とプライバシー権の調整問題ではあるものの,立法府による規制の場合,市民対国の関係ですから,国家機関である裁判所は仲裁者ではありませんね。そうすると,機械的に,表現の自由VSプライバシー権=個別的利益衡量とすることは,危険であることがわかります。
では,裁判所が仲裁者である場合とは,どのような場合でしょうか?
このあたりは,みなさんで考えてみてください。
2 3つの審査基準
さて,違憲審査基準とは,合憲と判断するための条件であり,その条件が審査密度により変化すると言いました。
本来,その条件は,事案に応じて細かく細分化されるべきですが,ここでは,わかりやすさの観点から,4つに分類しておきましょう。
なお,この4つの分類は,平成20年採点実感4頁,作法67~69頁,芦部先生の『憲法判例を読む』(岩波セミナーブックス,1987年)103頁を参考にしたものです。
通説と沿っているかはどうかはわかりませんが,司法試験との関係では,この理解で十分であると考えております。
まず,審査すべき要素としては,次の4つが挙げられます。
①目的審査
②手段適合性審査
③手段必要性審査
④手段相当性審査
次に,違憲審査基準としては,次の4つが挙げられます。
A 厳格審査
B-1 LRAの基準
B-2 実質的関連性の基準
C 合理性の基準
※B-1とB-2をまとめて,B中間審査と呼ぶこともあります。
まとめると,次の表のようになります。
(1) 目的審査
①目的審査では,ⅰ保護法益の重要性(量×質)とⅱ害悪発生の確率の掛け算により審査をすることになります。
厳格審査ならば,「やむにやまれぬ必要不可欠な公共的利益」が必要となります(芦部188頁)。ちょうど,「明白かつ現在の危険の法理」に類似するテストをするものといえます。
具体的には,「①ある表現行為が近い将来,ある実質的害悪をひき起こす蓋然性が明白であること,②その実質的害悪がきわめて重大であり,その重大な害悪の発生が時間的に切迫していること」までをここで審査するイメージですね(芦部200頁)。
中間審査(=LRAの基準と実質的関連性の基準の双方)では,「重要な目的」が必要になります。
具体的には,保護法益が人権に還元し得るような重要なものであること,その害悪発生の確率が事実をもって基礎づけられていることが必要になると考えます。例えば,何かしらの事件が発生したため,これに対応するものとして立法された場合,害悪発生については,事実をもって基礎づけられていると言えますね。
合理性基準では,「正当な目的」が必要となります。これは,まぁあり得るよね,と言える程度でクリアするものですね。具体的には,ⅰ保護法益の重要性につき,ネガティブチェックのようなものしかせず,ⅱ害悪発生の確率につき事実に基礎づけられていなくても,予防的に規制することが許されるわけです。
※作法76~77頁とは考え方が異なります。また,芦部200頁では,明白かつ現在の危険の基準において,上記①②の他,「③当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠であること」が必要であるとあります。これは,上記の整理でいくと,手段審査で行うべきものなので,目的審査からは除外しました。
(2) 手段適合性審査
②手段適合性審査では,当該手段が目的を促進するか(=因果関係の有無),当該手段は目的との関係で実効性はあるか(=因果関係の程度)を審査することになります。
厳格審査,中間審査では,「実質的関連性」が必要になります。具体的には,目的と手段とのあいだに具体的・実質的な関連性がなければ,合憲ということはできません。薬事法違憲判決が,「競争の激化―経営の不安定―法規違反という因果関係に立つ不良医薬品の供給の危険が、薬局等の段階において、相当程度の規模で発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、確実な根拠に基づく合理的な判断とは認めがたいといわなければならない」としていることからもうかがえますね。
合理性の基準では,「合理的関連性」が必要になります。具体的には,「目的と手段とのあいだに抽象的・観念的な関連性があればよい」(芦部202頁),「具体的・実質的関連性は必要ないので予防的な規制を許される」(同203頁)というものです。
要するに,中間審査と合理性基準は,予防的な規制が許されるか否か,が最大の違いになるのです。
(3) 手段必要性審査
③手段必要性とは,当該手段を採用する必要性,換言すれば,より制限的でない他の選びうる手段があるか否か(=LRAの有無)を審査するものです。
規制そのものが必要かを審査するわけではありませんので,ご注意ください。それは目的審査に包含されています。
厳格審査及びLRAの基準では,合憲とするためにはこの審査をクリアする必要がありますが,それ以外の基準ではクリアする必要はありません。
(4) 手段相当性審査
④手段相当性については,不要論も存在します(芦部105頁[高橋先生執筆部分],作法69頁参照)。しかし,目的審査,手段適合性審査,手段必要性審査をクリアしてしまった場合であっても,なお不相当な規制を違憲にできる可能性があるという,いわばセーフティーネットのような機能は期待できるため,相当性の審査は必要であると考えます(読本79~80頁参照)。
厳格審査の場合,「過剰でもなく,過少でもない」ことが必要になります。過剰ではないとは,過度に広汎ではないこと(=過大包摂でない・副作用がない),過少ではないとは,取りこぼしは許されないこと(=過少包摂でない)をいいます(争点282頁(松井茂記)参照)。
その他の基準の場合,「過剰でないこと」が求められますが,この部分は,結局は個別的利益衡量をするしかありません。
※手段相当性不要論は,まさに手段相当性が個別的利益衡量であるから,裁判官の思考を拘束しようとした違憲審査基準論の趣旨に反するとして,手段相当性を否定しているわけです。なるほど,不要論の立場も理解できなくはありません。高橋先生は,目的審査,手段の関連性を審査したら,手段相当性は擬制されるとすら説きます。しかし,目的審査,手段適合性審査,手段必要性審査において,上記のように思考の枠組みが決まるわけですから,最後の手段相当性だけが個別的利益衡量になるとしても,他の審査をせずに個別的利益衡量をするだけの審査よりは,裁判官の思考を拘束できるはずです。また,平成20年採点実感4頁は,明らかに手段相当性を論じることを要求しています。ですから,手段相当性不要論は,司法試験との関係では不要でしょう。
まとめ
・違憲審査基準は,裁判官の思考を拘束するために登場したもの。
・個別的利益衡量は,裁判所が仲裁する場合に限定して活用
・違憲審査基準をまとめると,以下の通りになる。
●次回予告
第5回は,「違憲審査基準論の使い分け」です。お楽しみに。
予備校憲法に革命を!
伊藤たけるの講義「憲法の流儀小教室」はこちらから。

司法試験・選択科目の選び方~知的財産法のすゝめ①~
法科大学院入試や期末試験も概ね終了している頃とは思います。
今回は,2014年,2015年に司法試験を受験する皆様は,そろそろ「司法試験の選択科目をどうするべきか」という問いに直面していると思われます。
私自信,知的財産法を選択いたしましたが,この決断は今でも正しかったと思います。
そこで,今回は,私がなぜ知的財産法を選択したか,どのような基本書,演習書を使用したかについてご紹介したいと思います。
※ただし,だからといって,この記事を無批判に受け取って,安易に知的財産法を選択するのはやめてくださいね。
私の判断過程を参考に,みなさん自身でしっかり選んでください。
1 司法試験の選択科目
(1)選択科目は8科目
司法試験の選択科目は,以下の8科目があります。
・労働法
・倒産法
・知的財産法
・経済法
・租税法
・環境法
・国際関係法(私法)
・国際関係法(公法)
なお,各科目の特徴は,LECの「新司法試験 選択科目の選び方」というレジュメを参照してみてください。
(2)ちょっと概論を知ってみる
さて,この8科目がありますよ,と言われたところで,どれを選んでいいかなんてさっぱりわかりませんよね。
そこで,LS入学前で時間があるという方は,概論を知ってみることが肝要です。
・労働法
労働法は,森戸英幸先生の「プレップ労働法」が読みやすいですね。
ご自身も認めているように,少し「ふざけすぎ」な感じはありますが,学生としては下手な予備校本よりわかりやすいです。
著者曰く,
「ぶっちゃけ新司法試験くらいならこの本(+ケースブック系の本を使ったロー・スクールでの講義)でも十分だと個人的には思っているのだが……」
「「入門書」と自ら銘打ったが,ただ「コンパクトで読みやすいけど,表現があっさりし過ぎててつまらない,したがってなにも頭に入らない」というよくあるタイプの入門書には絶対にしたくなかった。」
(初版のはじめにⅴ頁)
というものですので,労働法を試験科目にしないとしても,楽しく読める超良書です。
★プレップ労働法〈第3版〉 (プレップシリーズ)/弘文堂
¥2,100
Amazon.co.jp
・倒産法
倒産法は,イメージをつかむためには,山本和彦先生による「倒産処理法入門」が最適でしょう。
山本和彦先生は,倒産法の大家であるため,その記述の正確性は折り紙つきです。
実務に出る前にどうせ勉強するので,一読する価値はあります。
ただし,「プレップ労働法」と違って,あっさり系ですので,少し眠たいかもしれません。
★倒産処理法入門 第4版/有斐閣
¥2,310
Amazon.co.jp
・知的財産法
知的財産法については,私が習った小泉直樹先生の新書「知的財産法入門」が最適です。
小泉先生は,2013年1月時点で,TMI法律事務所の弁護士・弁理士でもありますが,元々は東大の助手を務め,現在は慶應義塾大学法科大学院教授という研究者です。
新書ですから,すらすら読み進めることができるので,オススメの1冊です。
★知的財産法入門 (岩波新書)/岩波書店
¥756
Amazon.co.jp
・経済法
経済法は,有斐閣アルマの「ベーシック経済法 独占禁止法入門」が非常にわかりやすいですね。
ケーススタディも多用されているため,イメージがつかみやすいです。
ベーシック経済法 第3版-- 独占禁止法入門 (有斐閣アルマ)/有斐閣
¥1,995
Amazon.co.jp
・租税法
租税法は,「プレップ租税法」あたりが無難でしょうね。
「税法入門」という本は,薄いのですが,めちゃくちゃ眠いので避けました。
プレップ租税法〈第2版〉 (プレップシリーズ)/弘文堂
¥1,785
Amazon.co.jp
・環境法
環境法も,いろいろありますが,やはり定番の「プレップ環境法」ですかね。
これしか読んだことがないのでわかりませんが。。。
プレップ環境法〈第2版〉 (プレップシリーズ)/弘文堂
¥1,260
Amazon.co.jp
・国際関係法(私法・公法)
この分野はあまり明るくないので,無責任なコメントは差し控えます。
2 選択科目の選定基準
さすがに,これだけ選択科目があると迷ってしましますね。
何を基準に選定するべきかは難しいところです。
「ボクのべんきょう日記~弁護士実務と司法修習と司法試験の巻~」というブログ(通称:ボクべん)のこちらの記事もありますので,読み比べてみてください。
私は,以下の5つを基準にしましたので,参考にしてみてください。
・何よりも自分が興味のあるものを選ぶ
・実務や就活のことは気にしない
・教材が充実している科目にする
・出題範囲が狭い科目を選ぶ
・大学・LS(ロースクール)にいい先生がいる科目にする
では,1つ1つ見ていきましょう。
(1)何よりも自分が興味のあるものを選ぶ
まずはご自身が興味のある分野があるならば,そちらを選択した方がいいでしょう。
なぜなら,司法試験の選択科目とはいえ,それなりの学習量が必要ですから,飽きずに勉強できるものがいいに決まっています。
私は,元バンドマンであり,今でもバンド関連の友人が多いため,知的財産法には強い興味がありました。
このような動機は,選択科目を決める大きな理由になると思います。
(2)実務や就活のことは気にしない
みなさんの目標は,言うまでもなく,司法試験の合格です。
ですから,実務に役立つとかは,正直どうでもいい事柄です。
「労働法や倒産法は実務で使うから就活に有利」というのも,あまり関係ないような気がします。
実務家は,専門の事務所でない限り,様々な法律を取り扱うことが要求されるようですから,選択科目が何であったかは,ぶっちゃけどうでもいいように思います。
もちろん,履歴書が書きやすいという効果は否定しません。
ですが,毎年,労働法選択者も倒産法選択者も山のようにいるわけですから,就活で選択科目がアドバンテージになるというのは考えにくいように思います。
無論,ある科目が大好きで,司法試験でも超上位1ケタを獲得してやる!という意気込みがあるならば話は別ですが,そうでない限り,選択科目を何にしたかは,そう大きく関係しないはずです。
(3)教材が充実している科目にする
司法試験の合格が目標であるならば,教材の充実度で選ぶ方が合理的となるわけです。
受験生の多い選択科目である程,教材が充実しているように思います。
需要が多いわけですから,供給も多くて当然ですよね。
私は,この基準を活用して,
・労働法
・倒産法
・知的財産法
に選択肢を絞りました。
他方,コンサルさんのブログは,これと異なる見解のようです。
抜粋すると,
「実力がある者や試験勉強なれをしている既習者は、予備校の講座や模試、テキストが豊富なメジャー科目を選ぶ傾向がある。そのため、マイナー科目では、実力者が少ないのだろう。」
「怠惰な人、純粋未習の人、必修科目に時間を割きたい人は、国際私法や経済法などのコスパの高い科目」がいいとのことです。
司法試験が相対評価であることから,この意見も説得的ですね。
(4)出題範囲が狭い科目を選ぶ
さて,そうすると労働法を選択したくなるところですが,ちょっと立ち止りましょう。
労働法と倒産法は,試験範囲が膨大です。
これに対し,知的財産法は,出題範囲に限定があります。
参照:法務省「平成18年から実施される司法試験(選択科目)における具体的な出題のイメージ(サンプル問題)」
この資料によると,出題範囲は以下のとおりです。
・労働法(3頁)
「労働基準法,労働組合法などの基本法令及び労働契約に関する判例法理を中心に出題するが,男女雇用機会均等法,育児・介護休業法,労働者派遣法など,実務上重要と考えられる労働法令についても基本的な理解があることを前提とする。」
※この資料が配布された平成17年12月1日当時は,労働契約法が制定されていないため,「労働契約に関する判例法理」となっています。
しかし,平成20年3月1日より労働契約法が施行されている現在は,「労働契約法」と読み替えるのが適切でしょう。
なんと,労働基準法,労働組合法,労働契約の3つも法律があります。
しかも,男女雇用機会均等法等,関連法令についても,基本的な理解が前提となるようです。
・倒産法(7頁)
「破産法及び民事再生法を中心として出題する。」
破産法と民事再生法という2つの法律が中心であり,会社更生法は試験範囲から除外されています。
その意味では,労働法よりは楽かもしれませんね。
・知的財産法(1~2頁)
「知的財産法においては,特許法と著作権法の2法を中心として出題することとし,実用新案法,意匠法,商標法,不正競争防止法等については,それ自体の知識や法律上の論点を問うことはしない。」
知的財産法では,特許法,著作権法の2つが中心となります。
ところが,知的財産法には,見慣れない「なお書き」があるのです。
「なお,特許法については,「総則」(目的,定義,補正関係),「特許及び特許出願」(特許の要件,発明の新規性の喪失の例外,特許を受ける権利,職務発明,特許出願,共同出願,先願),「審査」(拒絶の査定,拒絶理由の通知),「出願公開」(出願公開の効果等),「特許権」(特許権の効力,特許権の効力が及ばない範囲,特許発明の技術的範囲,他人の特許発明等との関係,共有に係る特許権,専用実施権,通常実施権,先使用による通常実施権,登録の効果),「権利侵害」,「審判」(拒絶査定不服審判,特許無効審判,訂正審判,共同審判,訂正の請求関係,職権による審理,審決の効力,訴訟との関係)及び「訴訟」を中心として出題する。また,著作権法については,「総則」(目的,定義),「著作者の権利」(「著作物」,「著作者」,「権利の内容」,「著作者人格権の一身専属性等」,「著作権の譲渡及び消滅」,「権利の行使」)及び「権利侵害」を中心として出題する。」
そうです。
特許法,著作権法のすべてが試験範囲なのではなく,その2つの法令の,しかも一部しか出題されないわけです。
これにより,試験範囲は相当限定されます。
(5)大学・LS(ロースクール)にいい先生がいる科目にする
残念ながら,選択科目は予備校に頼れる講師がいないため,LSの講義と自習が中心になります。
ですから,LSに進学している方は,LSにいい先生がいるならば,それを活用しない手はありません。
また,予備試験合格者の方も,大学の講義に潜るなりして,教授に質問することも大切でしょう。
ただ,結局は自学自習が中心になりますので,この指標はそこまで大きくないでしょう。
幸い,私が在籍していた慶應義塾大学法科大学院には,小泉直樹先生という知的財産法の素晴らしい先生がいらっしゃいましたので,これが決め手になりました。
以上の通り,私は,元バンドマンであり知財法に興味があったこと,教材が充実している科目であるにもかかわらず,出題範囲が限定されている上,小泉直樹先生に教えていただけるということから,知的財産法を選択しました。
ただ,小泉直樹先生の講義は,シッカリきいていなかったので,実際には自学自習がメインでしたが。。。
次回は,その自学自習の方法についてご紹介したいと思います。
お楽しみに。
知的財産法の勉強法~知的財産法のすゝめ②~(司法試験・選択科目)
1 知的財産法の特徴
特許法,著作権法ともに改正の激しい分野ですが,要するに,論点が条文で解決さているにすぎません。
特許法は,一部規範を暗記する必要がありますが,行政法の理解が深まるため,相互作用が期待できます。
他方,著作権法は,純粋な民事法であり,条文操作で片づけられる場合が多いですね。
ですから,基本的には,条文知識を入れることができれば,六法全書を武器に十分戦える科目といえます。
2 知的財産法の学習に必要な書籍
(絶対に必要は書籍には,アマゾンのリンクに★マークをしてあります)
(1)予備校教材は不要
自学自習がメインになるわけですから,基本書選びは極めて重要です。
正直なところ,選択科目については,予備教材は不要でしょう。
特許法の概要を知りたいのであれば,特許庁のウェブサイトのこちらがよくまとまっています(平成24年度知的財産権制度説明会(初心者向け)テキストより抜粋)。
(2) 基本書
ここで,私が使っていたものをご紹介しましょう。
・特許法
まずは,高林龍先生の「標準特許法」です。
★標準特許法 第4版/有斐閣

¥2,730
Amazon.co.jp
高林先生は,元裁判官であり,調査官経験もある先生ですから,端的でわかりやすいです。
・著作権法
また,著作権法は,島並良先生・上野達弘先生・横山久芳先生による「著作権法入門」を使っていました。
★著作権法入門/有斐閣

¥2,625
Amazon.co.jp
この本は,まさに司法試験のために必要最小限度のもので,少し深い論点も脚注でしっかり紹介されています。
記述はあっさりしていますが,読めば読むほどわかるようになる名著です。
・私の受験後に発売されたもの
なお,私の受験には間に合わなかったのですが,高林先生の「標準著作権法」も出版されております。
特許法の完成度からすると,使いやすいのかもしれませんね。
標準著作権法/有斐閣

¥2,625
Amazon.co.jp
また,私が講義を受けていた小泉直樹先生も教科書を執筆されているようです。
授業のレジュメがベースと思われますので,内容はかなり期待できます。
特許法・著作権法/有斐閣

¥2,520
Amazon.co.jp
(3)ケースブック・判例集
まずは,言うまでもなく判例百選ですね。
概要をつかむためにはもってこいの判例集ですから,絶対に購入して下さい。
★特許判例百選 第4版 (別冊ジュリスト209号)/有斐閣

¥2,520
Amazon.co.jp
★著作権判例百選 第4版 (別冊ジュリスト)/有斐閣

¥2,520
Amazon.co.jp
また,判例の正確なロジックやあてはめを学ぶためには,長めの判決文を読むことが必要です。
印刷するのが面倒であれば,ケースブックが便利です。
慶應義塾法科大学院の小泉直樹先生の授業では,弘文堂の「ケースブック知的財産法」を使っていました。
ただ,これを独習するのは厳しいでしょう。
ケースブック知的財産法 第3版 (弘文堂ケースブックシリーズ)/弘文堂

¥4,200
Amazon.co.jp
その他,重要判決については調査官解説を読みましょう,と言いたいところですが,選択科目にそんな時間は割けません。
そこで,調査官解説の速報版である時の判例を活用しましょう。
知的財産法は,民事系に含まれています。
最高裁時の判例―平成元年~平成14年 (3) (ジュリスト増刊)/有斐閣

¥3,360
Amazon.co.jp
最高裁時の判例 5―平成15年~平成17年 (ジュリスト増刊)/有斐閣

¥3,990
Amazon.co.jp
最高裁 時の判例(平成18年~平成20年)6 (ジュリスト増刊)/有斐閣

¥3,600
Amazon.co.jp
(4)演習書
司法試験を突破するためには,演習が必要不可欠ですね。
そこで,某予備校の演習本,,,という発想になりがちですが,知的財産法は,LS教員による素晴らしい演習書があります。
ハッキリいって,次の2冊だけで十分です。
これ以上時間をかける必要はないでしょう。
1つめは,田村善之先生の「論点解析 知的財産法」です。
この本は,オリジナルの演習問題のほか,司法試験の解説まである「受験指導本」です。
おまけに答案例までついています。
初版からの誤植がそのままのところがありましたが,品質はぴか一ですね。
どうしても時間がなければ,この本を回して完璧にするだけで十分でしょう。
★論点解析 知的財産法/商事法務

¥3,570
Amazon.co.jp
お次は,「知的財産法演習ノート」です。
こちらは,小泉直樹先生指定の教科書でした。
一部,関西弁による会話形式の解説が読みにくいのですが,議論水準は極めて高い良書です。
前掲の「ケースブック知的財産法」との相性もよく,独習に向いています。
知的財産法演習ノート―知的財産法を楽しむ21問 第2版/弘文堂

¥2,940
Amazon.co.jp
(5)参考書
なお,特許法,著作権法ともに,中山信弘先生という大家がいらっしゃいます。
しかし,残念ながら,中山先生の著作は試験との関係では不要です。
ちょうど会社法でいうところの江頭先生の位置づけですね。
辞書として購入するか,図書館で参照する程度にしましょう。
著作権法/有斐閣

¥4,410
Amazon.co.jp
特許法 第2版 (法律学講座双書)/弘文堂

¥4,410
Amazon.co.jp
3 具体的な勉強方法
以上が書籍の紹介でした。
具体的な勉強方法としては,以下の通りでしょう。
(1)LS2年時
前期:特許法
後期:著作権法
ともに基本書を読みながら,百選やケースブックで判例を学習する。
必要に応じて,「論点解析知的財産法」を解く。
(2)LS3年時
前期:特許法,著作権法の双方につきひたすら「演習ノート」を解く,時の判例を読み込む
後期:「論点解析知的財産法」をひたすら回す。
(3)予備試験合格者の場合
予備試験合格者の方は,上記の順番で早回しすることになるでしょう。
最悪,「演習ノート」はカットしても大丈夫だとは思います。
以上,知的財産法の勉強方法でした。
結局,選択科目は,自学自習するしかありません。
最低でも,★のものは購入することを強くお勧めします。



